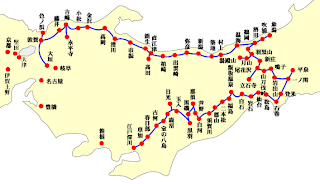水曜日, 10月 24, 2012
ドナルド・キーンの『俳諧入門』(その一~その八)
ドナルド・キーンの『俳諧入門』(その一)
(目次) 1 序(ドナルド・キーンの『俳諧入門』)
2 俳諧の連歌の登場
3 松永貞徳と初期の俳諧
4 談林俳諧
5 蕉風への移行
6 松尾芭蕉
7 芭蕉の門人
8 俳諧の中興
9 徳川後期の俳諧
余章・川柳(別に掲載)
・蕪村の「謎の細道」(別に掲載)
・蕉門十哲と現代俳人(別に掲載)
(参考文献)
『日本文学史(近世篇上)』ドナルド・キーン著・徳岡孝夫訳
(中央公論社・昭和五一)
『日本文学史(近世篇下)』ドナルド・キーン著・徳岡孝夫訳
(中央公論社・昭和五二)
『日本文学史』小西甚一著(講談社学術文庫・平成五)
(補注)
1 人物の年齢などは、西洋暦に換算されており、他の図書等と、陽暦と陰暦の関係で一年のズレがあるものもある。
2 特殊文字等のいくつかについて、現代常用漢字等を使用している。
3 上記の図書のうち、1と2の要約引用は、特に明記していない。なお、上記図書以外の参考文献は、本文中に明記してある。
第1 序(ドナルド・キーンの『俳諧入門』)
ドナルド・キーンに、『俳諧入門』という著書があるわけではない。ドナルド・キーン
の不朽の名著『日本文学史』を目にして、この著書から、彼になりかわり、ドナルド・
キーンの『俳諧入門』というような、そんなものが出来ないものであろうか。
そんな思いに囚われたのは、彼の俳諧の発句(俳句)に対する天才的な英訳が、俳諧に不案内な者にとって、興味と正しい理解を、強烈にインプットするのではなかろうかとう、そんな単純なことが、その動機となっている。
およそ、日本の古典、中でも、芭蕉とか蕪村とかの俳句や、その文章に接すると、直接・間接を問わず、受験戦争の後遺症か、実に、そのアレルギー現象を起こす方が、実に多いという事実・、これは、実に想像を絶するものがある。
芭蕉の『おくの細道』を読んでいると、それだけで、「専攻は国文学」ということとなる。そのように思っている人達の言い分は、「現代国語すら理解出来ない者が、どうして、得体の知れない古典といういかめしい国語を理解することが出来ようか」という諦めにも似た心情なのである。そして、その人達の大部分は、驚くべきことに、多くの他国の歴史や現状についての興味と正しい理解とを身につけているのである。
このこともまた、直接・間接を問わず、受験戦争の後遺症とも思われるのでる。すなわ
ち、本来、ドナルド・キーンの、この『日本文学史』の読者層になるべき人達の多くが、かって「英語・現代国語・世界史」の三科目にしぼり、それ以外は、我関せずで良しとしていたのである。(そして、このことは、今の若い人達にも等しく当てはまることでもある。)
この現象を、現代国語以外の、古典国語(古文)という観点から換言してみると、それ
は、「古典国語(古文)というジャンルは、英語というジャンルと同じように、他国語というジャンルに均しい」ということに他ならない。
このようなことを頭におきながら、ドナルド・キーンの、その生涯をかけてのライフワ
ークともいうべき、この『日本文学史』にかかわる作業というものを概括した場合、それは、実に多くのことを暗示してくれる。
この『日本文学史』は、日本の国文学の研究者としての、ドナルド・キーンが、英語圏
の人達を対象に、英文で書いたものを、さらに、今度は、日本人(徳岡孝夫)が、日本語に翻訳するという、いはば、二重に手間と時間を割いた貴重な書なのである。
それだけではなく、編集者と訳者とのアイデアで、この著の詩歌には、原著にある英訳
が、そのまま併載されているという、これまた、大変に魅力に満ちたものなのである。
そして、さらに、その英訳は、「原著者(ドナルド・キーン)によれば、必ずしも詩的完成を第一とせず、読者の理解を助けるのを主目的とした」とあり、この『日本文学史』から、その俳諧にかかるところを、単純に編集しただけで、これは、優に、現在刊行されている、この種の俳諧に関する入門書より優れたものになることは、この著書に触れたものが、等しく認めるところのものであろう。
では、何故、そのようなものが実現しなかったのであろうか。それは、ドナルド・キー
ンその人、あるいは、ドナルド・キーンより依頼された人が為すべきであって、その他の第三者が、妄りに関与してはならないというような、そんな不文律の故からなのかも知ない。
しかし、もし、このような不文律に理由があるとすれば、その不文律はクリアされなけ
ればならない。何故ならば、この『日本文学史』にかかわる一連の作業を見ていくと、それは、丁度、歌仙における付け合いのような、そんな思いがするのである。
すなわち、原著者・ドナルド・キーンの『日本文学史』が、歌仙における発句で、その
訳者(徳岡孝夫)による『日本文学史』が、脇句で、この発句と脇句は、その第三の付けを待っているように思われるのである。
そして、その第三の付けとは、編集者と訳者のアイデアで、この著の詩歌に、原著の英
訳が併載されているところから、ドナルド・キーンの『俳諧入門』ということも、それほど、違和感のある付けとは思われないのである。
要は、いかに、原著者・ドナルド・キーンの名を辱めないか、心すべきことは、この一
点である。そして、それ以上に、歌仙における第三の付けは、発句と脇句の詩的な世界
から大きく飛翔しなけれならないというルール下にある。
とすれば、少々の脱線も、少々の異論も、必ずや、原著者・ドナルド・キーンも、その
訳者(徳岡孝夫等)も、許容してくれるものと、座を同じうする者としての確かな手応えに似たものも感じとっている次第である。されば、ここ暫くは、ドナルド・キーン一座の、『俳諧入門』という歌仙興行をたっぷりと堪能して頂きたいのである。
第2 俳諧の連歌の登場
1 露ものいはぬ山吹の色
The dew lies silent over
The color of yellow roses.
2 霞にも岩もる水の音はして 宗鑑
Even in the spring mists
One hears the sound of water
Trikling throughthe rocks.
中世の末期、貴族的な連歌から、庶民的な、滑稽・卑俗・平易を旨とする「俳諧之連歌」(俳諧・連句)が興り、山崎宗鑑( そうかん・1465?~1553? )荒木田守武( もりたけ・1473~1549)らの手によって形成されていった。俳諧が連歌から独立する動きである。
宗鑑の名がはじめて記録にあらわれるのは、1488年で、当時まだ二十代の彼は、宗
祇( そうぎ・1421~1502 )、肖柏( しょうはく・1443~1527 )、宗長( そうちょう・1488~1532)らの大師匠と連歌を一座し、その時の宗鑑の一句が上記の2 の句である。
この宗鑑の句は、俳諧師・宗鑑というよりも連歌師・宗鑑が、表の芸としての連歌の興
行のあとで、余興としての、即興的・機知的な言葉の遊戯として、その後の「俳諧之連歌」の先鞭をつけているような句と理解できるのであろうか。
この2 の宗鑑の句の即興的・機知的・滑稽味というのは、「1 の句の露が、silen
t( ものいはぬ)なのに比して、もっと、( ものいはぬ)と思われる・の句の霞が、sound( 音をたてている)」という、この対比の妙にあるのであろう。
しかし、「俳諧之連歌」というのは、もっと卑俗な飄逸さをもったものへと転化を遂げていくのである。
3 あぶなくもありめでたくもあり
It is dangerous
But also makes us joyful:
4 婿入りの夕べに渡る一つ橋守武
The log bridge
We cross in the evening
To welcome the groom.
3 の前句は、典型的な謎かけの句で、後の川柳の前句付けの源流ともいえるものであろ
う。守武が、この謎の謎解きをしているのである。ドナルド・キーンは、この句を「一家が丸木橋を渡って婿入りを迎える」情景としてとらえているが、「婿となる人が丸木橋を渡ってくる」ともとれる句であろう。どこにも、卑猥さのない、ほのぼのとした、五七五の川柳的な句作りといえるであろう。
5 にがにがしくもをかしかりけり
Bitter,biter it was
But it was also funny.
6 わが親の死ぬるときにも屁をこきて 守武
Even at the time
Why my father lay dying
I still kept fathing.
何とも、悪趣味の付けであるが、5の前句の、見事なまでに謎解きをしている絶妙な機知的な付けではある。こういう句は、後の、川柳というジヤンルのものであり、このような、俳諧の系譜を辿っていくと、川柳こそ、「俳諧之連歌」(俳諧・連句)の本流であったことが理解されてくる。
7 霞のころもすそはぬれけり
The garmennt of mist
Is damp at the hems.
8 なはしろをおひたてられて帰る鳫(かり) 宗長
Chased away from
The bed for rice-plants,
The wild geese depart.
9 佐保姫のはるたちながら尿(しと)をして 宗鑑
The Godress Sao
Now that spring has come,pisses
While still standing.
7 の句が、前句で、8 と9 の句が、その付句である。7 の前句の意味は、「春霞で、その霞の裾のほうは、ぼやけて水に濡れているようだ」の意味であろう。8 の句は、連歌師としては、俳諧風の自由かつ想像力に満ちた創作をしたことで知られる宗長の句であるが、その滑稽味は、やはり連歌風で、微温的なところに止まっている。
9 の句は、宗祇の十三回忌の1514年に、宗鑑によって編纂されたとされている『新撰犬莵玖波集』の冒頭の宗鑑の句である。「春の女神の佐保姫が立小便して、裾が濡れた」とする、この着想の奇抜さは、これこそが、俳(たわむれ)諧(たわむれ)風の連想の飛躍なのであろう。『新撰犬莵玖波集』が、俳諧最初の撰集とされる所以も、ここにあるのであろう。
そして、これらの俳諧の連歌が、俚謡などのように詠み捨てにされてしまわずに、この
『新撰犬莵玖波集』の中に収められ、今に語り伝えられている事実は、それは、とりもなおさず、俳諧がその初期の段階において、すでに文学的価値ありと認められていたという、一つの証左になるものなのだろう。
ドナルド・キーンの『俳諧入門』 (その二)
第3 松永貞徳と初期の俳諧
1 霞さへまだらに立(たつ)やとらの年 貞徳
Even the mist
Rises in spots
The year of the tiger.
2 ねぶらせて養(やしなひ)たてよ花のあめ 貞徳
Let him lick themー
That’s the way of bring
him up:
The flower sweets.
3 しほるゝはなにかあんずの花の色 貞徳
Do they droop because
Of some grief? The apricot
Blossomes’color.
4 皆人のひる寝のたねや秋の月 貞徳
Is it the reason
Why everyone is nappingー
The autumn moon.
後世に、俳諧の祖といわれる宗鑑や守武は、宗長・宗牧と年齢の差はあるが、同時代の
人であり、両者とも、それら連歌作者と交渉を持つ、彼ら自身、連歌作者でもあった。
宗鑑は、『新撰犬莵玖波集』を編み、守武は『守武千句』を出し、後世にまで千句形式の
範となった。その後、この二人の活躍を吸収した人、それが、松永貞徳(ていとく・15
71~1653 )である。
貞徳の下には、松江重頼( じゅうらい・1602~1680)・野々口立圃( りゅうほ・
1595~1669 )・ 安原貞室( ていしつ・1609~1673 ) などの俊英が参集
した。これらは、貞門派と称され、貞徳自身、後世に、近代俳諧の祖と仰がれるに至った。
上記の貞徳の四句は、重頼が編纂した『犬子(えのこ)集』のもので、『犬子集』とは、
宗鑑の『新撰犬莵玖波集』の子の意味であろう。
1 の句の面白さは、「寅の年には、霞も、斑な寅の斑点がある」という洒落であろう。
2 の句は、貞徳が子を儲けた人に贈った句で、懸詞( かけことば) と縁語の巧みさがポイ
ントの句で、連歌の知識がないと、なかなか理解し難いとされている。ドナルド・キーン
の懇切丁寧な訳がある。
「子に飴をねぶらせてすこやかに育てよ、雨が花を育てるように。そして、釈迦にあやか
ってあなたの愛児の上にも花の雨が降るように。」
3 の句は、「あんず」( 杏 )と「案ず」との懸詞の巧みさと「花の色はうつりにけりないた
ずらに 我身世にふるながめせしまに」( 小野小町) の故事が巧みに組み合わされいるとこ
ろが見どころの句である。
4 の句は、取りつき易い句で、「前の夜の月見で、皆んな昼寝をしている」という滑稽味
が中心の句である。
貞徳は、俳諧のほかにも、多くの和歌や連歌も残しているが、当時の最も新しい文学運
動の俳諧の旗手として、なかんずく、俳諧式目制定という面で多くの業績を残し、貞門俳
諧は、全国津々浦々に至るまで、その支持者を持つに至った。
しかし、貞徳の死後、その門弟間に争いが生じ、貞門の名声も次第に翳りを落とすこと
となる。
5 これはこれはとばかり花の吉野山 貞室
Look at that! and that!
Is all I can say of the
blossoms
At Yoshino Mountain.
貞徳の真正後継者を自負する貞室の代表的な句である。この句は、芭蕉によって高く評
価された、今日でもよく知られられた句の一つである。吉野山の満開の桜、ただただその
賛嘆に我を忘れる・・、調べが自然で、貞門俳諧の技巧ばしったところが少しも見当たら
ない。より、次の時代の、芭蕉の時代の雰囲気である。
6 巡礼の棒ばかり行く夏野かな 重頼(維舟)
Only the staffs
Of the pilgrims are seen going
Through the summer fields.
『犬子集』を編纂した重頼、後の維舟は、まったく平気で、師の貞徳が定めた俳諧の作
法を破り、後に、貞門から離れ、彼独自の別派をつくるに至った。その別派とは、貞門俳
諧の次の西山宗因を中心とする談林派俳諧へと通じていくのであった。
この重頼の句も、貞門特有の懸詞・縁語は見当たらず、むしろ写生の清新さが目立つ句
といえる。
第4 談林俳諧
西山宗因(1605~1682)が、はじめて重頼に会ったのは、1625年頃のこと
らしい。二人の交遊は、やがて終生続くものとなる。 宗因の俳諧は、のびのびとした軽
いトーンで、彼が大阪天満宮の連歌宗匠に主任したことは、新風の首領として担ぐには最
適な人物であった。宗因は、その新風の談林俳諧の総帥となるのであるが、実際の主唱者
は、大阪の井原西鶴(1642~1693)であり、これに呼応したのが、江戸の田代松意(しょ
うい・生没未詳)や京の菅野谷高政(生没未詳)であった。
1 おらんだの文字か横たふ天つ鳫 宗因
Is that Dutch writing?
Across the heavens stretch
A line of wild geese.
黄檗宗の僧になった宗因が、本山のある長崎へ旅行した時の句である。横一列になって
渡る雁を、オランダの横文字と見立てるところに、この句の趣向がある。
2 さればこゝに談林の木あり梅花(うめのはな) 宗因
I have discovered here
There is Danrin tree・・
The plum blossomes.
1675年の春、江戸に下った宗因は、田代松意らの俳席に招かれる。その俳席での千
句巻頭の、宗因の発句である。季題は、梅で、宗因の号である梅翁にも通じている。宗因
自らが、談林俳諧の総帥たらんことを宣言した句である。
3 末茂れ守武流の惣本寺 宗因
May it flourish forever,
The great central temple of
Moritake’s style.
1678年、宗因が京へ行った時の、京に住む菅野谷高政に送った句である。惣本寺は、
高政が自らの結社を称していた名で、貞門俳諧の貞徳が、宗鑑を高く評価していたのに対
し、談林の俳人達は、その裏を行き、守武の古典俳諧の流れと称していたのであった。
4 菜の花や一本(ひともと)咲きし松のもと 宗因
The rape-seed blossoms・・
A single stalk has flowered
Under the pine tree.
宗因の晩年の句である。ここには、鋭い自然観察の眼がある。より高度の俳諧への兆し
が読み取れる句でもある。松の沈鬱な緑を背景に、ただ一本の菜の花のあざやかな黄が、
春の訪れを告げている・・、談林風の俳諧は、ともすると、俳諧の規矩を忘れ放埒に過ぎ
たとの批判を受けるのであるが、晩年の宗因には、その批判は当てはまらない。 いずれ
にしろ、談林風の俳諧の最盛期は、ごく短いものであった。1 6 7 5 年から1 6 8 5 年までの、たかだか十年位のものに過ぎない。
5 心こゝになきかなかぬか時鳥(ほととぎす) 西鶴
Is my mind elsewhere?
Or has it simply not sung
Hototogisu.
西鶴が、宗因の門弟になったのは、十四歳か十五歳の時で、この句は西鶴の初期の句で、
その二十四歳の時に上梓された撰集の中に収録されている。この句は、『大学』の「心ココ
ニ在ラザレバ見レドモ見エズ、聞ケドモ聞エズ」を踏まえての「なきかなかぬか」の巧み
な技巧の句作りといえよう。後に、西鶴の作風は、その奇抜さの故に、「阿蘭陀(オランダ)
流」と呼ばれるようになる。 西鶴は五十二歳で、その生涯を閉じるのであるが、彼の天
才ぶりは、いろいろの形で世の語りぐさとなっている。彼は、矢数俳諧(やかずはいかい)
の記録保持者でもあった。1684年の大矢数では、実に、一昼夜で、二万三千句という
空前の事業を成し遂げた。 現在では、その談林風俳諧のエースとしてよりも、『好色一代
男』などの、近代小説への一代舵取りをしたということで、その名を馳せている。
ドナルド・キーンの『俳諧入門』(その三)
第5 蕉風への移行
それぞれ自説をかざして貞門と談林との主導権争いは、1680年頃には頂点を達した。江戸でも大阪でも両者の不毛の争いが続くのであるが、この不毛の揚げ足取りの論争に飽き足らずにいた少数の俳人達は、新しい俳諧の道を模索していた。 その俳人達とは、もと貞門の人であった伊藤信徳(しんとく・1634~1698) や池西言水(ごんすい・1650~1722)あるいは談林系の上島鬼貫(おにつら・1661~1738)・小西来山(らいざん・1654~1716)・椎本才麿(さいまろ・1656~1738)らであつた。 この人達は、俳諧史上に不朽の名声を止めるまでには至らなかったが、彼らの一人ひとりが、やがて芭蕉が到達すると同じ道を同じ方向に歩いていたということは、強調しておく必要があろう。
その道は、芭蕉を得ることによって、ようやく本格的な俳諧の誕生を見るに至る。短い表現の中に、単なる警句的な機知の閃き以上のものを蔵した俳諧、偉大な詩人の心に宿った詩想を一つの凝縮として表現し得る俳諧の世界が、芭蕉の出現によって開けるのである。
1 富士に傍(そう)て三月七日八日かな 信徳
Following by Fuji・・
It was the sevennth day or
The eighth of April.
信徳は、京の豊かな商人で、商用で諸国によく旅をした。1677年、江戸に下った時
は、芭蕉や山口素道(そどう・1642~1716)と『江戸三吟』を巻いている。この句は、1685年の「旅行」と前書きのついている句で、「七日八日(なぬかようか)」という語感の冴えが見事である。言葉を選びながら、言葉の遊戯に陥らないところは、極めて、芭蕉の句に近いといえる。
2 名月や今宵生るゝ子もあらん 信徳
The harvest moon!
Tonight there must also be
Children being born.
ドナルド・キーン氏の見事な評を全文引用してみる。「信徳晩年のこの作は、すでに年老いたわが身にひきくらべて、今宵生まれる満月のようにすこやかな子もあろうかという思念を含蓄しているばかりでなく、実は、その子さえ満月の欠けていくのと同様にやがて人生の終焉を迎えるこそあわれよ、という詠嘆がこめられている。これだけの短く素直な表現に、これだけの人間感情がうたい込められているとは、ほとんど信じられぬくらいだが、幼な子と無欠に達していまや欠けなんとする月の取り合わせにこそ詩人としての信徳の真の意図があるのであり、老いて月を眺める寂寞の情緒もそこからにじみ出てくるのである。」 信徳は、後に、「蕉風の先駆」と呼ばれるようになるが、事実、若き日の芭蕉は、この年長者の信徳から多くのことを学んだことであろう。
3 うの花も白し夜半(よなか)の天河(あまのがは) 言水
The verbenas blossoms too
Are white:in the middle of night
The milkway.
池西言水も、信徳と同じように、まず、貞門に学び、ついで談林に移った人である。言水は、まだ世に知られていなかった頃の芭蕉と交わり、芭蕉の作品を、自撰の『東日記』(1681年)などの中で紹介し、芭蕉が世に知られる一つのきっかけを作っている。この句は、談林の絶頂期の、1678年の作で、芭蕉俳諧の趣を、この頃から、すでに、言水は自分のものとしていたのである。「季節は夏。夜の闇に卯の花の白さが浮き出ている。白さはやがてくる秋の夜、天の川が中天にかかるころを思わせる。」(ドナルド・キーン)
4 鯉はねて水静也郭公(ほととぎす) 言水
A carp leaps up
And now the water is still:
A nightingale.
「芭蕉の有名な古池の句とあまりにも情景が似ているので、つい比べてみたくなる作で
ある。言水の句は制作の年月がわからないが、どうやら芭蕉のより先の句であるらしい。言水の自注によると『この里のさびわたるにはほとゝぎすもやと待わびしに、さはなく里魚のはねる音をきく。いやましに淋し。はたして時鳥なりけり』という。句はこうした言水の体験をみごとに十七字の中に描きえている。そこには漢詩の影響も認められる。だが、やはり古池の句の絶対無二の響きに比べると、一歩劣るところがあるのを認めないわけにはいかない。」(ドナルド・キーン)
5 凩(こがらし)の果はありけり海の音 言水
The winter wind
Had a destination,Isee:
The roar of the see.
「海に出て木枯帰るところなし」は、山口誓子の昭和十九年の作、この句がほうふつし
てくる句である。ともあれ、誓子の木枯の句についての、誓子の自解を見てみよう。
「『木枯』は、木を吹き枯らす風、秋の末から冬の初めにかけて吹きすさぶ。『凩』という字は、日本で造った字だ。風の中に木がある。まさに木を吹き枯らす風だ。 私は、海の家にいて、図上を吹き通る木枯の音を聞いて暮らしたるその木枯は陸地を通って、海に出る。直ぐの海は、伊勢湾だが、渥美半島を越えると、太平洋に出る。太平洋に出た木枯は、さえぎるものがないから、どこまでも、どこまでも行く。日本へは帰ってこない。行ったきりである。『帰るところなし』、出たが最後、日本には、帰るべきところはないというのだ。昭和十七年作に、『虎落笛叫びて海に出で去れり』という句を作ったことがある。もがりぶえは、冬になって、笛を吹く強い風だ。その強風がひゅうひゅう云って、海に出て去って行ったのだ。この句があって、これを下敷きにして『帰るところなし』の句が出来たのだ。俳句は積み重ねだ。」(山口誓子『自選自解説 山口誓子集』)
時に、誓子は、四十三歳、太平洋戦争の真っ只中にあった。句としては、誓子の方が、言水を上回るものであろう。しかし、芭蕉以前の俳人にして、このような句があるということは驚きですらある。
6 白魚やさながらうごく水の色 来山
The whitebait ------
Just like the color of water
Itself moving.
これは、来山の句である。勿論、芭蕉の『野ざらし紀行』の「あけぼのやしら魚白き事一寸」が連想してくる。芭蕉の初案形は、「雪薄し白魚しろき事一寸」が知られている。とにかく、芭蕉の前後の俳人には、芭蕉の名吟に匹敵するような作品を残している幾人かの俳人が存在したということは注目する必要がある。すなわち、芭蕉という大俳人が俳諧史上突然現れたというよりは、芭蕉のような大俳人が現れる素地が、当時の俳諧史が内包していたということの方が正しいように思われるのである。
7 見かへれば寒し日暮の山ざくら 来山
When I look behind me
How cold they look ------ the twilight
Mountain cherry blossoms .
来山は、大阪談林の一方の雄であるが、この句などは、談林風というよりも、次の時代の蕉風の句であろう。談林俳人達の多くのように、言葉遊戯の俳諧という世界を脱して、五七五という短い詩形をもって、自己の感情を表出するという、蕉風の世界の中に来山の姿を見出すのである。
8 春の夢気の違はぬがうらめしい 来山
A spring dream ・・
I am not out of my mind
But how bitter I am .
この句は、1712年来山五十八歳の時の作品である。「浄春童子、早春世を去りし」という前書きがある。「うらめしい」とう口語の調べが、来山の悲痛さを詠出している。
9 幾秋かなぐさめかねつ母ひとり 来山
How many autumns
Did she spend unconsoled?
My mother,alone.
来山は、九歳にして父を失い、母の手一つで育てられた。十歳にして談林風俳諧を学び、十七歳の時はすでに宗匠として認められるに至った。その才能は天賦的なものであった。この句は、「わが心なぐさめかねつさらしなや をばすて山にてる月をみて」(古今集)からの連想であろう。
1 0 春雨や火燵のそとへ足を出し 来山
The spring rain------
I move my legs outside
The foot warmer.
句の冒頭に置かれた主題(春雨や)に、それに一つのイメージを添えて一句に仕立てる技巧の冴えは、来山が得意としたところのものである。そして、この句の、「しとしととふり続ける春雨の倦怠感(アンニュイ)」は、後の蕪村の世界のものである。蕪村にも、炬燵の句が多い。
○ 巨燵出てはや足もとの野河哉
○ 宿替へて火燵うれしき有り所
○ 腰ぬけて妻うつくしき火燵哉
○ 身ひとつの鳰のうきすや置き巨燵
1 1 春雨や降ともしらず牛の目に 来山
The spring rain------
Reflected in ox’s eyes
Unaware it falls.
「しとしとと降る雨の情感が、雨を雨とも感じずに鈍く開いた牛の目にうつり、詩人の
心は春の憂いのなかに沈んでゆく。」(ドナルド・キーン) この句などは、次の時代の芭蕉の時代を越えて、まさしく、その次の蕪村の時代の句を見る思いである。
12 庭前に白く咲きたる椿かな 鬼貫
In the front of the garden
It has whitely blossomed・・
The camellia.
「まことの外に俳諧なし」は、上島鬼貫の俳諧理念である。鬼貫の「まこと」とは、何
よりも貞門・談林の技巧過多に対比しての簡潔さであり、目に映る対象の真実に迫ろうとする真摯な創作姿勢をいう言葉であろう。ごく自然に心眼に映ることを、何の粉飾や技巧を付加することなく、そのままに表現することを、鬼貫は俳諧の創作理念とした。この句は、その鬼貫の「まこと」の俳諧の創作理念に基づく一つの現れであろう。
1 3 夕暮は鮎の腹見る川瀬かな 鬼貫
Are the close of day
You see sweetfish bellies
In the river shallows.
「夏のたそがれ、ものみな色を失って、白と黒だけが弁別される世界の中に沈んでいこ
うとしている。そんなとき、ひるがえる鮎の白い腹がきらりと光る。瀬は浅く、深まりゆく闇の中で、明澄な水の中に一瞬の躍動がある。」(ドナルド・キーン)
1 4 行水の捨どころなきむしのこゑ 鬼貫
Nowhere to throw
The water from my bath・・
The cries of insects.
鬼貫の句のなかで、世に知られている句の一つである。加賀の千代女の「朝顔に釣瓶とられてもらひ水」と同じような句作りということになろう。自然に対する優しい作者の心が伝わってくるが、その誇示が月並みな感情を醸しだしているともいえる。
1 5 此秋は膝に子のない月見哉 鬼貫
This autumn
I’ll be looking at the moon
With no child on my knee.
鬼貫も子に先立たれた。その時の句である。来山のそのときの句(8)と比較すると、両者の作風の相違が分かってくる。鬼貫の句には、来山のような悲痛な叫びというのは聞こえてこない。そこには、素直な表現を通して、鬼貫のメランコリックな感情の吐露があるに過ぎない。鬼貫は、嘘偽りのない「まこと」の俳諧を志した。そして、その極限は、いわゆる「芸術性の喪失」と「無技巧の月並みさ」の句へとつらなっているとも思われる。十七文字を用いて真に詩と呼ばれるべきものを創造するためには、単に、「まこと」だけでは十分ではないのである。そこに、芭蕉のように、「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、其貫道する物は一なり」(『笈の小文』)までの、芸術性の付与と絶えざる工夫が必要とされる。それには、芭蕉の出現を待たねばならないのである。しかし、芭蕉の出現には、鬼貫の「まこと」の俳諧が必要とされたのである。このことを、服部土芳の『三冊子』は、次のようにいっている。
「師の風雅に万代不易あり、一時の変化あり。この二つに究まり、その本一つなり。その一つといふは、風雅の誠(まこと)なり。」
すなわち、芭蕉俳諧の究極の理念である「不易流行」は、鬼貫の「まこと」をその根底にして発展したものともいえるであろう。 このように見てくると、芭蕉の出現というのは、突然に、芭蕉という天才がが出現したというよりは、その時代の趨勢が、芭蕉という天才を必要とし、そして、その時代が、芭蕉という天才を誕生させたということがいえるのかも知れない。
ドナルド・キーンの『俳諧入門』(その四)
第6 松尾芭蕉
ドナルド・キーンは、小西甚一著『日本文学史』の解説において、次のような一文を寄せている。
「『日本文学史』の最も有名な部分は、恐らく日本文学における『雅』と『俗』の分析であろう。序説の中にも『完成』と『無限』という二つの極に対する憧れを芸術の世界で考えると、〈前者を『雅』、後者を『俗』とよぶこと」にされたと説明されている。また、〈かような雅と俗との性格を、日本における表現の世代に当てはめるならば、古代は俗を、中世は雅を、近代は別種の俗を、それぞれの中心理念とし、大きく三分されるように思うのである〉と述べられる。これは示唆に富む観察であり、小西先生の俳諧文学論の特徴を為す。」
このことを、さらに、小西甚一のその著によれば、「雅」と「俗」との混合態としての「俳諧」という概念を認めており、中世から近代の過度期として近世という名称を与えることもできそうだとし、それは、俳諧の世代だとしている。
そして、小西甚一命名の「俳諧の世代」のチャンピオンが、それがまさしく、松尾芭蕉(1644~1694)、その人ということになろう。
芭蕉は生前すでにして偶像であった。旅する先々で多くの人々の注目と関心を集めた。そして、その芭蕉の旅は、新しい句風の樹立の旅でもあった。その生涯にわたる芭蕉の旅は、後世に五つの紀行文を残した。それは、・『野ざらし紀行( 甲子吟行・かっしぎんこう)・1 6 8 4 』、・『鹿島詣( 鹿島紀行)・1 6 8 7 』、・『笈の小文( 卯辰紀行・芳野紀行)・1 687』、・『更科紀行・1688』そして・『おくのほそ道・1689』の五つである。
ここで、便宜上、芭蕉の生涯を、・『野ざらし紀行』以前、・「『野ざらし紀行』から『おくのほそ道』まで、・「『おくのほそ道』以後の三期に分け、その句風の変遷の跡を追ってみよう。
1 『野ざらし紀行』以前
1 春や来し年や行きけん小晦日(こつごもり)
Has the spring come
Or has the old year departed?
The night before New year’s Eve.
今日知られている芭蕉最初の句で、1 6 6 2 年、芭蕉の1 8 歳の作品である。芭蕉は、この頃、彼最初の俳号の宗房を名乗り始めている。古今和歌集の「年の内に春はきにけりひととせをこぞとやいはん ことしとやいはん」の詞と詩想に基づくもので、貞門俳諧の技巧性が色濃く見受けられる句である。
2 姥桜咲くや老後の思ひ出(いで)
Old---lady cherry blossoms------
Have they flowered? A final
Keepsake for old age.
1664年に刊行された松江重頼編の『佐夜中山集』に収録された芭蕉の一句である。姥桜は葉の出ないうちに咲く花で、その「葉なし」を姥の「歯なし」に掛けている。詞は謡曲の『実盛』から来ている。これもまた貞門俳諧の流れの句である。
3 梅の風俳諧国(こく)に盛んなり 信章(素堂)
A plum---scented wind
In the land of haikai
Blows triumphant.
4 こちとうづれも此時の春 桃青(芭蕉)
Even for the likes of us
This is the spring of the age.
1 6 7 6 年の山口素堂と行った連句両吟であり、二人は既に談林の新風下にあったことを物語っている。梅は、「梅翁」で知られている宗因であり、・の素堂の句は、談林俳諧の伸長を宣言するものであった。・の芭蕉の句は、その素堂の付句で、「こちとうづれ」は「こちたちづれ」の転化で、「自分たちのような者」と卑下した言葉で、当時の芭蕉の談林俳諧との関わりが見えてくる。当時、まだ、芭蕉の号は見られない。
5 芭蕉野分して盥(たらひ)に雨を聞夜(きくよ)哉
Bash0 tree in the storm------
A night spent listening to
Rain in a basin.
芭蕉が江戸に出てきたのは、1 6 7 2 年、2 8 歳の時であった。そして、宗匠として一家をなしたのは、1 6 7 7 年の頃であり、その最初の門弟に、宝井其角・服部嵐雪・杉山杉風らの名が上げられる。その杉風の深川の下屋敷に移ったのは、1 6 8 0 年のことであり、門弟の李下が、この杉風の下屋敷に、一株の芭蕉を贈った。実を結ばない芭蕉の木は、わずかな風にも裂ける葉の故に、繊細な詩歌の心を象徴するものとして珍重されていた。この芭蕉の木が生い茂り、この深川の閑居を門弟達は芭蕉庵と呼ぶようになり、1682年頃から、芭蕉という号が使われだした。
この句は、1681年の頃の作で、当時の芭蕉庵の情景をよく写している。上五の字余
りは、芭蕉がなお談林風の影響下にあったことを物語っているが、談林風の笑いの裏面としての人生の侘しさという面に芭蕉の関心が移ってきていることを伺わせる句である。
6 かれ朶(えだ)に烏のとまりけり秋の暮
On the wintered branch
A crow has alighted------
Nightfall in autumn.
1681年の池西言水が撰んだ『東日記』の中の一句である。中七の句形は談林風の影響を宿しているが、水墨画などの「寒鴉枯木」という主題を、十七字で見事に言い現している。「枯枝に下りた烏は瞬間の観察であり詩中の『いま』であり、それは静寂のうちに迫りくる秋の夜のとばりへ向かって等号を引かれている。枯枝と烏は、助け合って互いにその心象を明確にしているが、照応は単なる修飾のためにあるのではない。一致して、時の中にありながら時を超えた瞬間を創造するための照応なのである。」(ドナルド・キーン)
1 6 8 3 年、蕉門最初の撰集である其角の『虚栗( みなしぐり)』を刊行する。芭蕉は、その跋文において、集中の句が、その風体において「李杜が心酒を甞(なめ)て、寒山が法粥(ほふしゅく)を啜(すす)る」ものであり、侘ひと風雅においては、「西行くの山行をたづね」また「白氏が歌を仮名にやつし」たものと自薦している。
これら、『東日記』(1680年)、『俳諧次韻』(1681年)そして『虚栗』に至る撰集は、著しく漢詩的情趣に傾斜した句風で、芭蕉の「虚栗調時代」といわれている。
ドナルド・キーンの『俳諧入門』(その五)
2 『野ざらし紀行』から『おくのほそ道』まで
1 野ざらしを心に風のしむ身かな
Bones exposed in a field------
At the thought,how the wind
Bites into my flesh.
2 秋十(と)とせ却而(かへって)江戸を指ス故郷
Autumn・・this makes ten years;
Now I really mean Edo
When I speak of‘home.’
3 猿をきく人すて子にあきのかぜいかに
What would poets who gived
To hear monkeys feel about
this child
In the autumn wind?
4 馬に寝て残夢月遠しちゃのけぶり
I dozed on my horse------
Half in dreams,the moon distant;
Smoke of breakfast tea.
5 手にとらば消(きえ)んなみだぞあつき秋の霜
Taken in my hands it would melt,
The tears are so warm------
This autumn frost.
6 道のべの木槿(むくげ)は馬にくはれ鳧(けり)
Mallow flower
By the side of the road------
Devoured by my horse.
7 死にもせぬ旅ねの果(はて)よ秋のくれ
I haven’t died,after all,
And this is where my travels
led------
The end of autumn.
1 6 8 4 年から8 5 年まで九ヶ月のあいだ、江戸を出て伊勢・伊賀・大和・山城をめぐり、近江から尾張に至ったこの旅は、その要点だけを記した短い紀行文にまとめられる。刊本として世に出たのは1689年、芭蕉の死後であった。これが、『野ざらし紀行(甲子吟行)』である。
「野ざらし」のいわれは、冒頭の1 の句によっている。1 の野ざらしの句では、芭蕉は路傍に行き倒れて白骨をさらすわが身を思って戦慄する。2 の句では、1 の前句の感情を殺しながら、すでに十年を暮らした江戸を郷里とも思う気持が述べられている。
『野ざらし紀行(甲子吟行)』の全体の調べは、主題そのものが唐宋詩文から採られたものや、故事に合わせて整えられてものが見られるなど、漢詩文の徹底的な影響下にある。3 の句は、空虚をかきむしる「猿嘯哀」の、唐詩などによく使われる主題である。「どれほど悲痛な猿の泣き声でも、貧しさのゆえに子を捨てねばならなかった人の親の苦痛にくらべようもない」という句意であろうか。
4 の句は、もっとも明瞭に漢詩の影響が見てとれるものである。晩唐の詩人・杜牧(803~852年)の次の五言律詩「早行」の中の一節に基づく連想であろう。
乗鞭信馬行 鞭を垂れ馬に信(まか)せて行く
数里未鶏鳴 数里 未だ鶏鳴ならず
林下帯残夢 林下 残夢を帯び
葉飛時忽驚 葉飛んで時に忽ち驚く
野ざらし紀行の目的の一つには、母の一周忌の墓参りのことも上げられるであろう。 5 の句は、伊賀上野に着いたときの芭蕉の絶句である。「母の部屋をめぐる草も霜枯れに枯れ、兄は『お互いにまだ生きて』と言ったきり絶句する。ややあって彼が開いてくれた形見の袋には母の白い遺髪。芭蕉は、それを手にとって、しばし嗚咽する。」(ドナルド・キーン)
6 の句、「芭蕉は、馬の背にゆられている。と、突然に馬が首を下げて食いとったのは,道ばたの生け垣に咲く一輪りむくげの花である。花がまさに食われようとする瞬間に、芭蕉の心はその美しさに気づいてときめく。どこかであった情景の紹介でもなければ、架空の出来事でもなく、一瞬の嘱目の吟である。」(ドナルド・キーン)
故郷の上野からさらに大和・山城・近江・美濃と旅した芭蕉は、大垣で門弟の谷木因(ぼくいん・1646~1725年)の家に止宿する。その時の句が7 である。江戸を出たときの、路傍に白骨をさらす暗い予感は、ここに至ってようやく晴れる。
芭蕉と木因は、相携えて桑名から尾張へと旅する。尾張着は1 6 8 4 年陰暦十月のことである。蕉風を代表する七部集の一番目に数えられる『冬の日』五歌仙の唱和が成ったのは、このときであった。
8 霜月や鶴(かう)の彳(つく)々ならびいて 荷兮
The eleventh moon・・
Storks listlessly
Standing in a row.
9 冬の朝日のあはれなりけり 芭蕉
How touching the morning sun
Of a winter’s day.
『冬の日』の由来は、集中第五の歌仙「霜月の巻」の芭蕉の・の脇句によっている。その発句は、・の山本荷兮(かけい・1648~1716)のものである。わずか一年半の『虚栗』にくらべて、もう、ここには漢詩文調の重々しい響きはない。『冬の日』は、蕉風確立の基とされている。
1 0 海くれて鴨の聲ほのかに白し
The see darkens:
The voices of the wild ducks
Are faintly white.
五・七・五の破調の句である。「暮れゆく冬の海の暗さを背景に、ほの白い微光が鴨の声の印象を支えている。絶妙の効果である。同時に読む者を感動せずにはおかない一句である。」(ドナルド・キーン)
1 1 なつ衣いまだ虱をとりつくさず
My summer clothes------
I still haven’t quite finished
Picking out the lice.
京から近江へ歩いた野ざらしの旅は、1685年陰暦四月の江戸帰着によって終わりを
告げる。この句が紀行最後の句である。ここには、巻頭の沈鬱な響きは影を落としてはいない。ここには、紀行を完遂した達成感と開放感に満ちみちている。
1 2 古池や蛙飛(とび)こむ水のをと
The ancient pond------
A frog jumps in,
The sound of water.
1 6 8 5 年に江戸に戻ってからの芭蕉は、翌8 6 年の陰暦正月に、其角をはじめその門弟達と『冬の日』の調子を承けた『初懐紙』百韻を催している。そして、その年の春、芭蕉は開眼の一句を得る。
「人間が永遠を知覚するためには、それをかき乱す一瞬がなければならない。蛙の飛躍、その一瞬の合図となった『水のをと』は、俳諧における『今』である。しかし、『今』が感知された瞬間に、古池は再びもとの永遠に戻っている。」(ドナルド・キーン)
永遠なるもの(古池に象徴される永遠なるもの)と瞬間的なもの(蛙の飛躍にともなう水の音)とを対比させることによって、芭蕉は、たった十七文字の中に宇宙を創造することに成功したのである。 この古池の句は、1 6 8 7 年に上梓された七部集の第二の『春の日』( 荷兮) に収められている。
1 3 髪はえて容顔蒼し五月雨
My hair has grown back
And my countenance is pale:
Rainy month of June.
七部集の第二撰集『春の日』が上梓された翌年、1 6 8 6 年、芭蕉は再び旅心に誘われ、鹿島神社へと、陰暦八月の十四に江戸を立ち、その二十五日ころに帰庵するという短い旅を実施する。この旅の記は、『鹿島紀行』にまとめられている。この頃のものとされている自詠の句が、13の句である。じめじめとした五月雨が降っている。外出もできず、不精をして伸ばした髪と青白い顔をして、芭蕉は、次の旅の計画を練っていた。鹿島から戻ってわずか二ヶ月後の1 6 8 7 年陰暦十月二十五日に、芭蕉は再び旅に出る。
1 4 旅人と我名よばれん初しぐれ
“Traveller”------is that
The name I am to be called?
The first winter rain.
旅そのものも順調であった。伊勢・尾張を経て故郷の上野に戻り、さらに、吉野・奈良
をたどって須磨に至る。このときの旅の記が、『笈の小文』である。この『笈の小文』が刊行されたのは、芭蕉の死から数えて十五年後の1709年のことであった。
「旅人と我名よばれん」とは、この『笈の小文』の「西行の和歌における、宗祇の連歌
における、雪舟の絵における、利休が茶における、其貫道する物は一なり」をうけ、自分(芭蕉)も第五の「旅人」という漂泊詩人としての心意気を示すものであろう。
1 5 草臥(くたびれ)て宿かる比(ころ)や藤の花
Worn out by my travels,
I rent a room at the inn------
Just then,wisteria bloosoms.
「草臥て」という自然な口語調、「宿かる比や」と暮春のたそがれの景、そして、行き暮れて宿借るころに、「今宵のあるじ」としての藤の花を見出したのである。
1 6 ほろほろと山吹ちるか瀧の音
With a soft flutter
How the yellow roses drop------
The roar of the falls.
「山鳥のほろほろとなく声きけば父かとぞ思ふ母かとぞ思ふ」(行基菩薩・玉葉集)の古歌を思い起こさせる。岩間をごうごうと響きをたてて落ちる滝、そして、弱々しく「ほろほろ」と散る山吹、リズムの感覚の優れた句である。
1 7 ほとゝぎす消行方(きえゆくかた)や島一つ
There in the direction
Where the cuckoo disappeared------
An island,just one.
「句に動きある。遠くへ飛び去るほととぎすを追っていた視線が、その姿の消えるとこ
ろで影を認める。語の配置された順次、そして音の静かな下り調子が、その動きをみごとに再現している。」(ドナルド・キーン)
18 鷹一つ見付てうれしいらこ崎
A solitary hawk------
How happy I was to find it
At Irako Point.
1 9 いらこ崎似る物もなし鷹の聲
Irako Point------
Nothing even resembles
The voice of the hawk.
2 0 夢よりも現(うつつ)の鷹ぞ頼母(たのもの)しき
Even more than the dream
The hawk of reality
Reassures me.
伊良古崎は万葉や西行のころから鷹で有名な土地がらであった。『笈の小文』の芭蕉は、芭蕉開眼第一の撰集『冬の日』の名古屋連衆の一人・坪井吐国の流謫の地、伊良古崎まで足をのばす。18の句は、伊良古崎でさびしく暮らしていた吐国に再会したときの、最終的な句形の句である。「さびしい浜辺に立った芭蕉は、漠々たる海と空に対している。と、遠くに一羽の放れ鷹。」(ドナルド・キーン)
19 は、その初案の句形。・は、別想とも(山本健吉著『芭蕉』)、しかし、「夢は、やがて後年の『嵯峨日記』の夢を予感している。現実に吐国に会うことは、彼を夢に見るよりもはるかに喜ばしいことだったのである」とし、この「三句を対比してみると、芭蕉が本質的に同じ材料を用いながらも、除々に深みと雄大さを増していき、最後に『鷹一つ』という絶対の句を探し当て、虚空無限のひろがりの中にただ一つの飛翔点を固定しえたことがわかる」とするドナルド・キーンの鑑賞視点は棄て難い。
『笈の小文』の、芭蕉と吐国とは、須磨まで足をのばし、『源氏物語』や謡曲『松風』などのゆかりの土地を訪ね、その須磨から京に戻り、そこで二人は別れる。吐国は、そこから流刑の地の伊良古崎へ、芭蕉は岐阜を経て尾張に向かった。
21 おもしろうてやがてかなしき鵜舟哉
Delightful,and yet
Presently how saddening,
The cormorant boats.
「岐阜長良川の鵜舟は、古来同地の名物だった。燃えさかる松明に惹きよせられる鮎を
呑んで上がってくる鵜、それを見守る人々の興奮、やがてしのび寄る悲哀の感情『おもしろくて』と言わず、わざと『おもしろうて』を使ったことが、見物人のわき立つような感興を端的にとらえ、それに痛々しさをこめた『かなしき』という音を続けることによって、鵜飼を見る芭蕉の気持の上昇と下降が写されている。」(ドナルド・キーン)
2 2 俤や姨(をば)ひとりなく月の友
I can see her now------
The old woman,weeping alone,
The moon her companion.
1 6 8 8 年陰暦8 月、越智越人( えつじん・1 6 5 6 ~ 1 7 4 0 ) と共に、美濃から信州へと向かう。この旅の記が『更科紀行』である。この句は、この更科紀行での一句である。其角の『雑談集』に、芭蕉がこの句は深夜の姨捨山を詠んだと語ったという。
2 3 木曽の痩もまだなをらぬに後の月
Still not recovered
From my thinness of Kiso------
The late moon-viewing.
こうして芭蕉は、ほぼ一年を留守にしていた江戸に帰着した。陰暦九月十三日、長旅か
ら帰ってきたときの、江戸の草庵での素堂以下との懐かしい顔ぶれとの後の月を賞しているときの句である。
24 行春や鳥啼魚の目は泪
Spring is passing by !
Birds cry,in the eyes of fish
Behold the tears.
更科の紀行より、わずか数カ月後の1 6 8 9 年の春、芭蕉の生涯最大の旅の『おくの細道』の旅をを決行する。その旅立ちは三月二十七日、春があと三日で終わらんするときだった。
「魚の目の泪は、イメージとしては超現実的なものだが、句が名詞止めになっているために芭蕉の感情表現が強められている。句は、まさに俳諧である。しかも、芭蕉でなければないような、軽みを持ちながらも哀切の余情を響かせている俳諧である。」(ドナルド・キーン)
「『奥の細道』は、言うまでもなく、みちのくへの旅なのだが、同時にそこには詩心の深奥への遍歴の意がこめられている。現在の旅に永遠の詩歌の探究を兼ねたこの表題そのものが、すでにして芭蕉の提唱した不易流行の理念を示唆するものと言えるだろう。先行する四紀行文の中にも、それぞれに美しい箇所はあったが、句と文が完全に融合し、それぞれに均衡を保ちながらもみごとな相互補完を演じるのには『奥の細道』を待たねばならなかった。しかも、収められている発句は名吟ぞろいであり、現代の名句集にも必ず収録されるものが、つぎからつぎへに織り込まれている。」(ドナルド・キーン)
2 5 夏草や兵(つはもの)どもが夢の跡
The summer grasses------
For many brave warriors
The aftermath of dreams.
「かってつわものどもの刀槍がきらめいた『昔』は、茫々の夏草が風にそよぐ『今』に
流転のさまを見せている。その哀切をとらえた名吟は、単にその意味するものだけではなく、句の中に配置された音によって一句に特別の強さを付与している。上五は母音がすべてアとウである。中七は、やはりアとウの繰り返しの中にオの音が連続して四つ、はさまっている。そして、下五は、『夢』という軽みを持った語に続いてオーアーオで句が締めくくられている。ためしに中の『兵どもが』を『兵隊たちが』とでもしてみれば、たちどころに原句の音の効果に思い至るであろう。」(ドナルド・キーン)
2 6 蛤のふたみにわかれ行(ゆく)秋ぞ
Parting for Futami
Dividing like clam and shells,
We go with the fall.
「貞門流の縁語、懸詞に満ちた句で、芭蕉の初期の俳諧修業への回帰が見られる。『ふたみ』は、これから伊勢へ向かう芭蕉が、二見ヶ浦を望むことを懸けながら、同時にはまぐりの蓋と身でもある。二見ヶ浦は貝の美味で知られるところだった。芭蕉は落ち合った門弟や友人とも別れ、再び一人になるのだが、貝の蓋と身が別れるようなつらい思いだという心をこめている。『行秋ぞ』は、また、江戸を出るときの『行春や』に呼応している。秋の句のほうも離別の悲哀をうたったものには違いないが、春の句にくらべると、その調子は軽快で、旅の終わりに近づいた芭蕉が、安堵の気持から、かって使った技巧を弄んでみたという趣きさえも感じられる。」(ドナルド・キーン)
この句をもって、『おくの細道』の記述は終わる。しかし、この後、二十年に一度の伊勢遷宮を拝観した後、1689年の九月末には故郷の伊賀上野に帰った。それからの二年は、京や近江を転々とし、何度か上野の旧居にも戻っている。
芭蕉は、琵琶湖の南、ことに、膳所と大津わ愛していた。1 6 9 0 年の正月を膳所で迎えた芭蕉は、その年の初夏に膳所藩の家臣だった菅沼曲水の世話を快く受け、湖南を見下ろす国分八幡の小庵に住んだ。そして、ここの約三ヶ月半の滞在の間に珠玉の俳文『幻住庵記』を書き上げる。
この時代の芭蕉は、おそらくその生涯で最も幸せな日々であったものと思われる。芭蕉
の遺言の中に一家の墓所の上野ではなく膳所に葬られるのを望んだのも、このことと関連するものと思われる。その年の晩秋には、膳所の義仲寺境内の庵に移った。後に、芭蕉の遺骸が埋められたところである。
ドナルド・キーンの『俳諧入門』(その六)
3 『おくのほそ道』以降
1 初しぐれ猿も小蓑ほほしげ也
First rain of winter------
The monkey too seems to want
A little straw raincoat.
「この句は、1689年陰暦九月、伊勢から伊賀へ向かう山路で芭蕉が得たものとされ
ている。冬近い山中、しぐれに降られた彼は、ふとわびしげな猿の姿を認める。ほほえみと同情をもって猿を見やる心は、とりもなおさず『猿蓑』全編を貫く心である。」(ドナルド・キーン)
1 6 9 1 年の正月を伊賀で迎えた芭蕉は、その春に京の嵯峨にあった向井去来の別宅「落柿舎」に移る。ここで、『嵯峨日記』を書き上げる。その後、京の門人の野沢凡兆の家に身を寄せ、ここで、去来・凡兆が編纂していた『猿蓑』の完成に携わる。芭蕉は、この『猿蓑』において「正風の腸(はらわた)」を見せんとの意気込みでその撰に没頭した。1691年陰暦六月に刊行された『猿蓑』は、全六巻から成り、芭蕉七部集のなかでもその頂点を究めたものとしてつとに名声を博したものであり、この句は、その『猿蓑』の巻頭を飾った発句である。
この『猿蓑』には、冬の発句(巻の一)、夏の発句(巻の二)、秋の発句(巻の三)、春の発句(巻の四)に続いて、巻の五は、歌仙(三十六韻の連句)が収められ、さらに、巻の六が、芭蕉の「幻住庵記」と関連の発句が収録されている。
この巻の五歌仙に、この撰集に携わった去来・凡兆と芭蕉の三吟歌仙が見られる。
2 市中は物のにほひや夏の月 凡兆
In the city
What a heavy smell of things!
The summer moon.
凡兆の日常の何気ないものを主題としている軽みの発句。発句は、季語(夏の月)と切
字(や)を含んでいなければならない。
3 あつしあつしと門々の聲 芭蕉
How hot it is! How hot it is!
Voices call at gate after gate.
芭蕉の脇句。発句の趣きを引き緊めている。韻字止めで発句と同じ季(あつしあつし)
が定石である。
4 二番草取りも果さず穂に出(いで)て 去来
The second weeding
Has not even been finished,
But the rice is in ear.
去来の第三。第三は変化の始まりである。「転じ」の定石に従って、場面は市中から田舎の場面と転換されている。発句が夏の場合は、三句続けてもよく夏(二番草)の句。「て」止めも第三の作法である。
5 灰うちたゝくうるめ一枚 兆
Brushing away the ashes,
A single smoked sardine.
平明かつ飄逸味のある「四句目ぶり」の軽い付けである。雑の句。
6 此筋は銀も見しらず不自由さよ 蕉
In this neighborhood
They don’t even recognize
money------
How inconvenient!
芭蕉は、自ら旅人となってその片田舎にやってくる。辺鄙な寒村なので人々は銀貨など
を見たことがないというのである。ここは「月の定座」なのだが、発句に定座が引き上げられている。雑の句。
7 たヾとひやうしに長き脇差(わきざし) 来
He just stands there stupidly
Wearing a great big dagger.
「とひやうしに」は、「突拍子に」の意味。全く突拍子も無く長い脇差であることよという句意であろう。雑の句。ここまでが、初折の表六句である。
8 草むらに蛙こはがる夕まぐれ 兆
In the clump of grass
A frog,and he jumps with fright
At the twilight hour.
「長い脇差」と「草むらの蛙」の取り合わせの滑稽味である。初裏の一句目、季語は蛙
で、春の句。
9 蕗の芽とりに行燈(あんど)ゆり消す 蕉
Going to pick butterbur shoots
The lamp flickers and goes out.
蕗の芽取りに行った若い女性が草むらの蛙に慌てふためいて手にしていた行燈かゆれて
消えてしまった。季語は蕗の芽、春の句。軽い受けである。
1 0 道心のおこりは花のつぼむ時 来
The awakening
Of faith began when the flower
Was still in the bud.
出家を思い立ったのは、まだ花もつぼみの頃でした。初裏十一句目の花の座が引き上げ
られている。春(花)。
11 能登の七尾の冬は住(すみ)うき 兆
The winters in Nanao
In Noto are hard to endour.
能登の七尾は寒さの厳しい所でとても住みづらい所であるという句意。出家した人の回
想の場面のようである。冬(冬)、季移り。
1 2 魚の骨しはぶる迄の老を見て 蕉
I have lived to see
Such old age Ican only
Suck the bones of fish.
若い頃は魚の骨など噛みくだくほど元気であったが、今では骨をしやぶるだけに老いさ
らばえた。述懐の句。雑。
1 3 待人入(いれ)し小御門(こみかど)の鎰(かぎ) 来
He let my lover in
With the key of the side door.
通用門を鍵でそっと開けて、主の恋人を中へ迎え入れました。前句の老いた人から門番
の翁の付けである。雑の恋の句。連句ははじめ百韻(百句)形式のものが主流を占めていたが、芭蕉の時代になってからは、三十六句をもって一巻とする歌仙の形式が多く行われるようになった。この歌仙三十六句のうち、最初の句を発句、二番目の句を脇、三番目の句を第三、一番最後の句を挙句と呼び、残りの四句目以下の三十句余りを平句(ひらく)と呼び、四季・月花・恋・雑などを交えて自在に変化していくところに連句の生命がある。芭蕉は、「歌仙は三十六歩也。一歩も後に帰る心なし」( 三冊子) と連句のこの流れの大切さを強調した。 また、芭蕉は、「文台を引下ろせば則反故也」( 三冊子)とも述べており、連句は元来、座の文芸であり、その制作していくプロセスを楽しむものであって、完成された作品を読んで鑑賞することが本義ではないという一面も有している。この座の文芸という一面から、連句を鑑賞・理解するということは、甚だ困難な点を有しているのであるが、芭蕉の俳諧を理解するということは、とりもなおさず、この連句を理解し、その上で発句を理解するという手順を踏まなければならないのである。そして、芭蕉は、「発句は門人の中、予におとらぬ句する人多し。俳諧においては老翁が骨髄」( 宇陀法師)と述べており、この面においては抜群の力量ぶりを発揮したのであった。そして、この『猿蓑』こそ、その芭蕉の俳諧(連句)の頂点を究めたものなのであった。この『猿蓑』完成後、再び、湖南・義仲寺に戻り、さらに、江戸に向かったのは、1 69 1 年陰暦の九月二十八日、江戸着は一ヶ月後だった。二年八ヶ月を留守していたこととなる。
14 病鴈(やむかり)の夜さむに落て旅ね哉
A sick wild duck,
Falling in the old of night:
Sleep on a journey.
「群れから離れて渡る病む雁と、旅の宿の夜寒に伏し悩む芭蕉の心境とが、言葉や技巧
を用いずして簡浄のうちにはっきりと連想される佳吟。彼晩年の詩境の到達点と言えるだろう。」(ドナルド・キーン)
『猿蓑』に、「堅田」との前書きのある発句である。この句は、1690年に湖西の堅田で病臥中の句で、すでに軽みを指向している句とされている。軽みとは、技巧や修飾的な手法とは反対の概念である。
それはまた、『おくの細道』にあるような高尚典雅な題材の「おもくれ」の句調と対比して、日常生活に句材を得るような「かるみ」の工夫を施した句調といわれている。
1 5 鹽鯛の歯ぐきも寒し魚の店(たな)
The salted bream
Look cold,even to their gums,
On the fishmonger’s shelf.
「1692年の冬の句、真冬の魚屋の店頭を叙したものである。一尾の鮮魚もない店の
盤台に、ちぢこまって歯をむき出した塩鯛が寒々とした雰囲気を伝えている。」(ドナルド・キーン)
この句の創作後の翌々年の、1 6 9 4 年に、志太野坡が編纂した『炭俵』とその年に大体の編集が完成していた服部沾圃編の『続猿蓑』( 刊行は1 6 9 8 年) は、芭蕉最後の連句撰集であるが、ここにおいては両者とも軽みを特色としている。
この「鹽鯛の」の句については、土芳の『三冊子』に、芭蕉の言葉が記録されており、
それによると下五の「魚の店」と具象的に詠んだことによって、日常性が加わり、その頃芭蕉が指向していた軽みへの工夫がみられるという。
1 6 麥の穂を便(たより)につかむ別(わかれ)哉
I clutch a stalk of wheat
To support me------
This is parting.
この句には、「五月十一日、武府を出て古郷に趣( おもむく)。川崎迄人々送( おくり)けるに」という前書きがついている。1 6 9 4 年陰暦五月十一日、芭蕉は郷里へと最後の旅に出る。江戸を出て、川崎での見送りの人々に対する留別の句である。
「おそらく近くに麦が見えたのであろう。心の杖ともたのんだできた弟子たちに惜別の情を残しながら、芭蕉はねこれからは麦の穂をたよりにするほかはないという心細い気持を述べている。」(ドナルド・キーン)
1 7 六月や峯に雲置クあらし山
The sixth month------
Clouds are resting on the peak
At Arashiyama.
この句には、「嵯峨」と前書きがある。故郷の伊賀上野に着いたのは、江戸を出てから十七日目であった。この上野から膳所・大津へと向かい、嵯峨の落柿舎に入る。その時の句である。この落柿舎に滞在中の六月八日に、芭蕉と深い係わりのある寿貞死亡の知らせを受ける。その七月中旬、盆会のために帰郷した芭蕉は、この数奇な運命を生きた寿貞に、「数ならぬ身となおもひそ玉祭り」という句を手向ける。
1 8 清滝や波に散込ム青松葉
Clear cascades------
Into the waves scatter
Green pine needles.
清滝は、洛北高尾を経て嵐山の上流あたりで大井川に合流する清滝川のこと。その激流
に、松の青葉が散り込むという芭蕉の心象風景ともとれる。この句は、芭蕉が最期の病床で手を入れた句である。
1 9 家はみな杖にしら髪の墓参
Everyone in the family
Leans on a stick: a white--haired
Graveyard visit.
郷里の盆会に戻り、一族の人々が墓参りに出かけたが皆白髪で杖をついているという芭
蕉の述懐の句であろう。この上野には、一ヶ月と少し滞在刷るのであるが、ここで、各務支考の助力を得て、『続猿蓑』の最後の編纂作業に携わる。上梓されたのは芭蕉死後の1698年であった。1694年の陰暦九月八日、芭蕉は上野を出て大阪に向かった。
2 0 此道や行人なしに秋の暮
Along this roard
There are no travellers------
Nightfall in autumn.
「所思」という前書きのある一句である。「夕風が吹きつのる秋の夕べ、孤独な旅人の悲愁である。」(ドナルド・キーン)
21 此秋は何で年よる雲に鳥
This autumn
Why do I feel so old?
A bird in the clouds.
「旅懐」という前書きのある一句である。「ここでも、孤影悄然の詩人が、雲に迷う鳥を見つめている。」(ドナルド・キーン)
22 秋深き隣は何をする人ぞ
Autumn has depened
I wonder what the man next door
Does for a living?
「明日の夜は、芝柏(しはく)が方にまねきおもふよしにて、ほつ句つかはし申されし」という前書きのある一句である。隣合って住んでいても、人間というのは、所詮、一人一人が生の営みをするものなのだという、晩秋の哀感の中に、人生の寂寥感を詠じている句であろう。
2 3 旅に病で夢は枯野をかけ廻(めぐ)る
Stricken on a journey,
My dreams go wandering round
Withered field.
「二十九日には、病状は悪化し、招宴に出ることはもはやできず、それからも病勢は進
む一方であった。十月五日には南御堂に近い花屋の離れに移された。宗匠病むの報は、たちまち弟子のあいだにひろまり、蕉門の人々がはせ参じて師の枕頭を囲んだ。その月の八日、芭蕉は弟子の一人に筆をとらせて最終吟を書かせた。十日の夜、支考に命じて遺書三通を代筆させた。草稿や蔵書の処置をたのみ、江戸の門人に別れを告げるものだった。それから、みずから筆をとって兄の半左衛門に一通を書いた。そのあとは、もう食事を受けつけず、静かに仰臥して死を待った。遷化は十月二日のことであった。通夜ののち、遺骸は舟で膳所の義仲寺へ運ばれ、遺言どおりに葬られた。荼毘に付したのちの埋葬は十四日。八十人に超える一門の弟子が会葬した。伊賀の門人二人には、郷里の家代々の墓に納めるべく遺髪が託された。」(ドナルド・キーン)
ドナルド・キーンの『俳諧入門』(その七)
第7 芭蕉の門人
芭蕉が江戸において宗匠として独立したのは、1678年、三十五歳になった新年のことであったとみられている。以後、次々と門弟の数を加えていくのであるが、堀切実はその蕉門の形成過程を五期に分けて概観している(『芭蕉の門人』)。
第一期:宗匠立机の年(1678年)から1680年陰暦四月の『桃青門弟独吟二十歌仙』刊行の頃まで。榎本其角(1661~1707)、服部嵐雪(1654~1708)、杉山杉風(1647~1732)らが一門を盛り立てていた。
第二期:1680の冬、三十七歳のとき深川芭蕉庵に入庵から1683年、四十歳頃まで。それまでの貞門・談林の俳風を乗り越えて、蕉風と呼ばれる新しい作風を樹立していく過度期である。其角編の『虚栗』(1683年刊行)によって代表される。
第三期:1684年、四十一歳を迎えて、はじめての文学的行脚である『野ざらし紀行』の旅に出てから、1687年の頃まで。この『野ざらし紀行』の旅の途中で、名古屋において、山本荷兮(かけい)、岡田野水(やすい)、坪井杜国(とこく)、加藤重五(じゅうご)らと『冬の日』五歌仙を巻く。これが、蕉風樹立の第一歩であった。郷里の伊賀上野の服部土芳(1657~1703)、北越生まれの越智越人(1656~1739?)らも加わった。
第四期:1687年初冬の『笈の小文』の旅の出発から,1689年、四十六歳のときの『おくの細道』の大行脚を経て、1691年初冬に江戸に帰着する頃までの時期。この二つの旅の経験を通して、蕉風がいよいよ円熟の境に達した時期である。向井去来(1651~1704)、野沢凡兆(~1714)らによる京蕉門の形成、内藤丈草(1662~1704)、各務支考(1665~1731)、立花北枝(~1718)、広瀬惟然(~1711)らも加わった。
第五期:1692年、芭蕉四十九歳の年から、その没する1695年までの三年間である。江戸では、其角・嵐雪が自立し、森川許六(1656~1715)が加わる。『別座鋪(べつざしき)』を撰した杉風グループ、『炭俵』を撰した志太野坡(1663~1740)グループが形成されていった。
これらの蕉門の形成過程の概括と併せ、堀切実氏は、新蕉門十哲として、其角・嵐雪・杉風・去来・丈草・凡兆・許六・支考・野坡・惟然の十人を上げている。
また、ドナルド・キーンは、「真に優れた作者だけに限定するなら、それは其角、去来、許六、それにもう一人、支考を加えた四人ではないかと思われる。」としている。
芭蕉の門弟が、その数において最も多かったのは、おそらく芭蕉の生地、伊賀の上野で
あろう。この伊賀蕉門の中の筆頭は土芳であろう。土芳は俳論集『三冊子』(1704年刊行)の著者として知られている。伊賀でのもう一人の高弟、窪田猿雖(1640~1704)も、芭蕉と極めて親密な友人でもあった。
江戸蕉門を代表するのは、其角と嵐雪であった。また、長年にわたって師に経済的援助を惜しまなかった杉風や深川芭蕉庵の近くに住んでいた河合曽良(1649~1701)も芭蕉と切っても切れない間柄であった。
晩年の芭蕉は京の近くに住むのを好み、その面から最も芭蕉に近かった者として去来が上げられるであろう。また、禅僧であった丈草も芭蕉に深く傾倒し、蕉門随一の「さび」の継承者として知られている。
彦根藩士の許六も、その俳論『俳諧問答』(1697年刊行)などで、芭蕉の高弟としての地位を不動のものとしている。また、少数の佳句を残して夭逝した吐国も、芭蕉が最も深い愛情を注いだ一人であった。
凡兆の客観的な句風も、後の蕪村らによって珍重される。さらに、支考に至っては、芭蕉の教えを俗化したとして毀誉褒貶の渦の中にいるが、その俳論は、全国各地で広く読まれ、蕉門随一の理論家として知られている。
野坡は『炭俵』の編者として軽みの人事句を得意とした。惟然もまた自然諷詠を主とする詩境に軽妙さを添え惟然風と称された。
とにもかくにも、芭蕉を取りまく俳人群像は多種多様で、現代俳論の随一の理論家とし
てその名を馳せた山本健吉は、「俳句は、かって芭蕉の時代に、それが連句の発句として達することのできた高さにまで, それ以後単独で到達したことは、一度だってない」(『俳句の世界』)とまで断言しているのである。まさに、至言である。俳諧、発句そして俳句という生命体において、その生命を持続している以上、常に、この氏の指摘もまた持続することであろう。
1 切られたる夢は誠か蚤の跡 其角
Stabbed in a dream・・
Or was it reality?
The marks of a flea.
蕉門の俳人の中で、最も早い時期に門弟となり、最も強烈な個性を発揮し、一時的には師の芭蕉を凌ぐほどの人気をはくし、後に、いかなる偶然によるものか、芭蕉の臨終に立会い、その死の床に横たわる芭蕉に『枯尾花』を手向けた其角は、その門弟の中でも一方の雄であろう。
去来は、この句について「其角は誠に作者にて侍る。わずかにのみの喰つきたる事、たれかかくは謂(いひ)つくさん」と、その『去来抄』で述べている。芭蕉も、その去来の言葉に、「しかり。かれは定家の卿也。さしてもなき事を、ことごとしくいひつらね侍る」と応えている。
芭蕉と其角とを対比してみると、芭蕉が推敲に推敲を重ね珠玉のような作品に仕立てていくのに対して、其角は即興吟を得意とし、当意則妙の機知をもってその場の関心をさらうということに関心があり、俳諧に関する根本的な姿勢が相違していた。
また、このことに関連して、芭蕉が高点を競う遊戯的な点取俳諧を排斥し閑寂な生き方
に徹したのに対して、其角は、江戸座随一の点取宗匠として華美伊達の生き方に徹したのである。
芭蕉が漂泊の俳諧師とするならば、其角は悠々たる定住の俳諧師ということになろう。其角の俳諧を通してのその交友関係は華麗なる一言に尽きた。俳号和英(わえい)こと画師・英一喋、俳号白猿(はくえん)こと歌舞伎役者二代目市川団十郎、俳号子葉(しよう)こと赤穂浪士大高源吾、俳号子山(しざん)こと一代の豪商紀国屋文左衛門など、実に話題の豊富な俳諧師であった。
其角は、十四歳の頃、芭蕉門に入ったらしい。その出発点は、蕉風俳諧史上画期的な、新風樹立を目指した芭蕉の意欲的な跋文を得て刊行された処女撰集『虚栗』(1683年刊行)であった。当時の空前の漢学隆盛時代を背景として、蕉風の詩精神を杜甫・白楽天に置こうとした、所謂、漢詩文調の『虚栗』の句風は、芭蕉と其角のコンビにより誕生したのである。
1684年、春から秋にかけて西上した其角は、難波の住吉神社で西鶴が催した一昼夜二万三千五百句の矢数俳諧興行の後見役をつとめ、京の伊藤信徳らとも俳交を重ねた。その西上から帰江後、1687年に『続虚栗』を刊行し、1688年に二度目の上方行に出て、京の去来・凡兆らと俳交を重ねた。
1691年に『猿蓑』集の序文を呈する栄誉を得た。文字通り蕉門筆頭の地位に立ったということになろう。芭蕉は、1695年の桃の節句に因んで、「草庵に桃桜あり、門人に其角・嵐雪あり」と称え、「両の手に桃と桜や草の餅」(『桃の実』)と詠んだほど、その信頼は厚かったのである。
しかし、1754年の許六あての手紙では、芭蕉は、其角のの俳諧について「拵(こしら)への俳諧」と指摘し、「其角・嵐雪の義は年々古狸よろしく鼓打ちはやし候」と、芭蕉と江戸の其角・嵐雪の間には亀裂が生じていくのある。それは、大衆の人気におもねようとする其角の洒落風俳諧に対する芭蕉の警告でもあった。
そして、この芭蕉と其角との間には、この亀裂のまま1794年の芭蕉の死をもって終
わるのである。そして、これもまた、何の因縁か、たまたま上方旅行中の其角は、芭蕉の臨終に侍するのである。その芭蕉没後は、ますます、其角の俳風は、奇抜な見立てや謎めいたものとなり、去来ら同門の其角評は厳しいものとなり、その批判の中で、さらには、江戸座の祖と仰がれつつ、1707年に、その四十六年の生涯を閉じたのである。
2 我(わが)奴(やっこ)落花に朝寝ゆるしけり 其角
My servant boy sleeps
This morning in falling
blosoms------
I have forgiven him.
この句には、白楽天の「惜花不掃地」という詞書がある。「散った花を惜しんで地面を掃かない」という意味である。この白楽天の詩の一節の外に、源公忠の「とのもりのとものみやつこ心あらば この春ばかり朝きよめすな」も、この句の背景にあるという。
さらに、ドナルド・キーンは、神田秀夫の「其角」(井本農一編『蕉門のひとびと』所収)の次の興味ある分析についても紹介している。
a 下僕が朝寝している。庭も掃かず荷にけしからん。
b おや、桜が散っている。
c この美しい朝の庭を見ないとは不風流なやつめ。起こしてやろう。
d いや、起こせば「どうも寝坊してすみません」と言うより早く掃い
てしまうだろう。
e やっぱり朝寝していてくれたほうがいい。黙っていてやろう。
f あるいは、あいつは俺のこういう気持を承知のうえで寝ているのか
な。心得たやつめ。
これが、其角の奇警な謎句の一つの正体なのである。このような句は、芭蕉の世界とは異質のものであろう。芭蕉の没後、其角は、このような句作りに終始したのである。そして、これが、機知と新奇を衒った江戸座俳諧の一面なのである。と同時に、俳諧は、常にこのような一面に走る本質を有して入るのである。このことは、よくよく心しておく必要がある。
3 湖の水まさりけり五月雨(さつきあめ) 去来
How the waters
Of the lake have swollen------
The fifth-month rains.
其角の1684年の始めての上方行において、去来との出会いがあった。そして、去来にとってこの其角との出会いが、それまで親しんでいた和歌から俳諧へと転回するきっかけとなった。
1686年の冬、江戸に赴き、芭蕉と対面する。以来、芭蕉の最も深い信頼を得て、晩年には蕉風俳論をまとめた『去来抄』を刊行する。この句は、去来の傑作句の一つで、1689年の『曠野(あらの)』に入集されたものである。許六は、この句に対して「予が心、夜の明けたる心地して、初めて俳諧の心(し)ンを得たり」(『俳諧問答』)とまで絶賛した。「茫洋たる湖と降り続く雨」との照合が、「取合せ論」を信奉する許六の眼鏡にかなったということであろうか。
この句が入集された『曠野(あらの)』が上梓されたその年の末、去来は京の嵯峨の落柿舎に芭蕉を迎える。ここで、去来・凡兆は、後に、「俳諧の古今集」(『宇陀法師』)とまでいわれた『猿蓑』を1691年に編纂する。この編纂過程のさまざまのエピソードが、その『去来抄』にまとめられている。
芭蕉没後の去来は、師風の継承に心を砕いたが、健康がすぐれず、その精進の自負とは裏腹に、自らも師風血脈の格調の高さを失っていった。其角との間においても、1697年の「晋子其角に贈る書」という長文の手紙により、芭蕉の遺風を忘れ、新しみを追求する志を忘れ、いたずらに、大衆におもねていると一喝して対立した。この其角と去来の対立は、さらに、許六と去来との対立へと発展していった。
それは、去来が「不易流行」論の立場を堅持するのに対して、許六は「血脈論」と「取合せ論」とをもって蕉風の新しい発展を志すとすることとの対立でもあった。いずれにしろ、芭蕉の没後、其角は其角、去来は去来、許六は許六の、それぞれが、それぞれの信ずる道を邁進したのである。
4 十団子も小粒になりぬ秋の風 許六
Dumpling on a string:
They too are smaller this year------
The winds of autumn.
1692年の秋、彦根藩士森川許六は、参勤交代で江戸に赴く途中、東海道宇都谷峠(静岡県の岡部と丸子両宿の間)で、この句を得た。後に、許六は、「取合せ論」を主張することとなるが、この句も、伝統的な雅の「秋の風」と日常的な俗の「十団子」の絶妙な取り合わせにより、宇津の山の旅情のわびしさを具象化させたところに、この句の生命がある。
この句は、当時、ひたすら新風の「かるみ」の境地を目指していた芭蕉に激賞される。時に、芭蕉四十九歳、許六三十七歳の時であった。
この1692年の秋から翌年にかけての丸九ヶ月が、芭蕉と許六との画俳二道の直接的な交流の場であった。ここで、許六は、芭蕉の新風の「かるみ」が、「腸(はらわた)の厚キ所」(『俳諧問答』所収「自讃之論」)から出るものでなければならないと説いている。これが、後に、許六の「血脈(けちみゃく)論」(「風雅の誠」の精神を継承することが蕉風俳諧の神髄とする許六の論)とつながっていく。そして、この「血脈」継承のための実際的方法として許六が力説したのが、その「取合せ論」なのである。
芭蕉の没後、1696年に、李由と共編で『韻塞(いんふたぎ)』、その年から1698年にかけて去来と『俳諧問答』の応酬をし、1702年には、李由と共編で『宇陀法師』を刊行し、1706年には『風俗文選』を編纂した。そして、1712年には『正風彦根躰(しょうふうひこねぶり)』を成して刊行した。
許六が没したのは、それから三年後の1715年のことであった。
許六の『篇突(へんつき)』(1698年刊行)が、当時、生まれ故郷の長崎に帰っていた去来の所に届けられた。この許六の『篇突(へんつき)』に対して、去来は『旅寝論』(1692年)を著すのであるが、この『旅寝論』は、その去来の著より六十余年後の、1761年に、雪中庵蓼太(大島蓼太)の跋を添えて『去来湖東問答』として刊行される。その蓼太の伝える、芭蕉の門人評は、実に興味深いものである。
「花やかなる事、其角に及ばず。 名月や畳のうえに松の影からびたる事、嵐雪に及ばず。 梅一輪一輪ほどの暖かさほどけたる事、丈草に及ばず。 蚊屋を出て又障子あり夏の月かろき事、 野坡に及ばず。 長松が親の名で来る御慶哉 実なる事、 去来に及ばず。 応(おう)おうといへど敲くや雪の門」
さらに、その序には、
「あだなる事、 土芳に及ばす。 たくみなる事、許六に及ばず。」の去来の序も見られ
るのである。即ち、芭蕉の門人達、その一人ひとりが、芭蕉のそれぞれの一面を自分のものとしていったのである。しかし、芭蕉その人を、芭蕉の全体としての俳諧を自分のものとし、それを正しく後世に伝えた人も、さらには、芭蕉その人を乗り越えようとした人も、蕉門十哲の門人においても、また、二千人とも三百人ともいわれている、その門弟の中においても、その名を見ることはできないのである。即ち、芭蕉の前に、芭蕉なく、芭蕉の後にも、芭蕉は存在しないのである。
第8 俳諧の中興
芭蕉が没すると、幾つかのグループに別れ、やがて四分五裂の状態となっていった。芭蕉の直弟子達が世を去ると、その傾向は一段と顕著となっていった。十八世紀の最初の四十年、つまり享保の頃の俳諧は、もはや昔日の面影を失ってしまったのである。
わずか十七文字の中に芭蕉がこめた威厳も、あるいは崇高な世界像も、もう、そこには
見ることはできなくなってなってしまったのである。
即ち、俳諧は、さまざまな意味において俗化していったのである。もう、そこには、深い感動や伝統への志向を託そうとするような意気込みは見当たらず、ただ、十七字を操って何か面白みを出そうとするだけの技巧のみが必要とされたのである。
それは、別な言葉でいえば、俳人達の関心事は、俳諧そのものよりも、その俳諧の技巧がもたらすお金の方に関心が向いてしまったのである。弟子を取り、点者としての宗匠の収入を増やすことのみに関心が向いてしまったのである。即ち、点取り俳諧の横行である。
このような点取り俳諧の横行は、其角の流れを汲む江戸の洒落風に代表される都市俳壇と、支考らの美濃派や岩田涼莵( りょうと) らの伊勢派などの地方俳壇と分化していった。
そして、この都市俳壇は川柳的な傾向と一線を画するのが難しいところまで俗化していき、また、地方俳壇の方は、俗語などを用いての平明さを金科玉条し、これまた卑俗化の方向に堕していくのである。
1 低きかたへ水のあわつや初あらし 沾徳
Foam on the water
Floats towards the Awaze
shallows
The first autumn storm.
其角の次の江戸座の代表的な俳人の水間沾徳(1661~1726)の句である。芭蕉の前の時代の談林風俳諧の最悪の類型への逆行が感じられる句でもある。
琵琶湖は、粟津の辺りで最も浅くなるので、秋一番の嵐は、湖の水を方へ吹き寄せてい
るというのである。水の泡と粟津の粟との懸詞である。
この沾徳は、「芭蕉発句はよき句あれど薄し。薄き所を得たる作者也。しかれども其角が強き程の句に芭蕉は力及ばず」(『沾徳随筆』)と、もはや、芭蕉は批判の対象となり、其角が彼らの崇拝する俳聖と化しているのである。
2 凩の一日吹いて居りにけり 涼莵
The winter wind
For one whole day blew
And kept blowing.
一方、地方俳壇の方も、卑俗・平明への道へとひたすら歩むこととなる。この句は、伊勢派の岩田涼莵(1655~1717)の句である。しかし、この卑俗・平明さは、俳諧の地方への普及という面では大きな役割を果たしたのであった。また、都市風の機知的な気障な作風よりは、まだ救いがあるという感じがなくもないのである。
3 朝顔に釣瓶とられてもらひ水 千代女
The well-rope has been
Taken by morning-glories------
I’ll borrow water.
支考の門に、加賀の千代女(1703~1775)がいた。1754年に剃髪して素園と称した。この句は、千代女の代表作であるが、機才に溢れ、その情緒的な面とその通俗性が、女流作家として俳諧史上にその名を止めている。
4 炭竃(すみがま)や鹿の見てゐる夕煙 巴人
The charcoal kiln- - - - - -
A deer watches
The evening smoke.
早野巴人( 1 6 7 7 ~ 1 7 4 2 ) の句である。別号を宋阿・夜半亭などと称した。下野国烏山の生まれ、江戸に出て、俳諧を其角・嵐雪に学んだ。両師の没後、俗化のきざしが出始めていた江戸俳壇を離れ、京都に移り住んだ。この間、望月宋屋( そうおく)・高井几圭( きけい) らの優れた門人を得た。1 7 3 7 年の頃、再び江戸に帰り、夜半亭と号し、この頃、与謝蕪村(ぶそん)が巴人の門人となった。
巴人が、1 7 3 9 年に其角・嵐雪の三十三回忌を記念して編んだ『桃桜』には、宰鳥の号での蕪村の句が見られる。蕪村が、後年、芭蕉の『虚栗』・『冬の日』の俳風を慕い、芭蕉の真髄を探ろうとした見識は、その師・巴人によって養われたのであった。
清廉にして俗俳になじまず、享保過度期の俳壇にあって、よく伝統を守り、中興俳諧の
礎となった俳人であった。
ドナルト・キーンは、巴人を二線級の俳人としているが、同時に、巴人のこの句に「写生」があるとし、この「写生」が、「明治期に入ると、俳句の優劣、とくに中興期俳諧の作品や作家の優劣の物差しとして重要視されるようになった」と指摘している。
いずれにしろ、芭蕉、そして、その後の蕪村をつなぐ接点に、この巴人の介在が必要と
されたのである。
5 柳ちり清水かれ石ところどころ 蕪村
Willow leaves have fallen,
The clear stream dried up,and
stones.
Are scattered here and there.
蕪村開眼の一句である。俳諧中興の中心となった蕪村( 1 7 1 6 ~ 1 7 8 3 ) は、芭蕉につぐ第二のは俳聖とそれている。大阪の毛馬村の出身とされているが、その生い立ちは定かではない。
蕪村は、生涯を通じて画人として知られることが多く、その生計も画業の方から得ていた。蕪村は、終生、芭蕉崇敬の念を持ちつづけるが、芭蕉的な求道的・献身的な、ただひたすら俳諧という道は歩まなかった。蕪村の態度は、むしろディレッタントのそれで、ただ極めて優れた俳力に恵まれたディレッタントだったのである。
「芭蕉と蕪村の相違は、なによりも両者の個性の差に由来する。芭蕉は、現実の積極的肯定によって貫かれた元禄の時代に生きたが、彼の詩精神は中世的、とりわけ西行や宗祇に近く、生活もまた中世の隠者のそれに近かった。一方の蕪村には、このような中世の吸引力がまったく認められない。彼は漢詩趣味、王朝趣味を愛し、俳画の中に捕えうる造形美への陶酔を持っていた。蕪村の宗教観は、芭蕉のような禅的直観力の中にはなく、むしろ狐狸の力への信仰の中にもっとも端的な表現をとっている。芭蕉には敬意を払いながらも、蕪村はついに自己を蕉風に同一化しようとはしなかった。」(ドナルト・キーン)
この蕪村の遊行柳の句は、その二十八才の頃の句であるが、西行を慕い(道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ)、芭蕉の『おくのほそ道』を慕い(田一枚植て立去る柳かな)、その師・巴人の「写生」を基礎に置き、詩性(漢詩的な詩心)をありのままに表現する蕪村俳諧の開眼の一句なのである。
6 絶頂の城たのもしき若葉かな 蕪村
On the pinnacle
The castle stands,confident,
Among strong young leaves.
「蕪村と現代人のあいだを遮る障害はなに一つない。現代日本文学中の最高の詩人であ
った萩原朔太郎が、江戸期俳人の中で蕪村だけに親和を感じ、彼の情操を『或る新鮮な、浪漫的な、多少西欧の詩と共通するところの、特殊な水々しい精神を感じさせる』としているのも、この親密を評価したものである。朔太郎は、蕪村の句の色彩の調子(トーン)の明るさと光の強烈さに印象派絵画への近似を発見し、若々しさと色彩を避けた芭蕉との対比において蕪村の若さを高く評価している。」(ドナルト・キーン)
この句も、城の白い壁と若葉の緑の視覚的なコントラストは、実に鮮やかである。上五
の「絶頂の」という強烈な句頭が効果的で、画人・蕪村の確かな写生眼を感じさせる。
7 遅き日のつもりて遠きむかしかな 蕪村
Long,slow spring days,
Piling up,take me far away
In the past.
「朔太郎が『浪漫的』と観じたこの句の調子は、繰り返される『O』の音、とくに『遠
き』の長母音により、いっそう明確にされる。遅々とした春の日がようやく傾く中で、ひとり白日夢の中にわれを忘れる蕪村の心は、遠い昔、おそらく彼が愛した平の昔へ、さまよい出でていくのであろう。」(ドナルト・キーン)
この句は、「懐旧」という前書きがついている。蕪村には、往時を追憶する作品が多いのであるが、この句も、白日夢のような夢想をさまようような句想であろう。それよりも、暮れおそい春の日の、身も心もけだるい、老の憂さ(アンニュイ)を感じさせる蕪村特有の句作りでもある。
8 さみだれや大河を前に家二軒 蕪村
The rainy season・・
The swollen river before them,
Two little houses.
「この句、渦巻き流れる濁流の岸にぽつんと置かれた二軒の家を、まざまざと眼前に点
出する。現代の蕪村研究家たちは、家は一軒でも三軒でもなく、どうしても二軒でなければならぬ点を指摘し、作者の技巧を高く評価している。しかし、この句がどれほどの感銘を与えても、そこには蕪村の心を占めてたはずの悲痛の情は、片鱗さえも見出すことができないのである。」(ドナルト・キーン)
「五月雨をあつめて早し最上川」は、芭蕉の『おくのほそ道』での句、この芭蕉の躍動的な調べに対して、蕪村のそれは、映像的な絵画的な視覚に訴える句作りである。ここに、決定的な両者の詩質の相違がある。
9 涼しさや鐘を離るる鐘の声 蕪村
The cool of morning------
Sparating from the bell,
The voice of the bell.
「このような句材、このような句境こそ、蕪村が俳諧の領域なりと信じたものであった。もし芭蕉が、このときの蕪村と同じ貧乏と家庭悲劇に襲われていたと仮定すれば、芭蕉は必ずやその逆境の中に沈潜し、ついには暗黒の中に一条の光明を発見しえたことであろう。だが、蕪村にとっては、俳諧そのものが光明であり、同時に情容赦のない現実からの逃避先であった。彼がとなえた離俗論が実際に意味していたのは、現実世界の暗さから目をそむけ、感覚世界の中に遊ぶ態度にほかならなかった。蕪村の句は、それが成立するに至った背景をほとんど考えることなしに鑑賞することができる。芭蕉の句は、それを年代順に並べ、旅行記その他の記述に照し合わせながら見ることによって、芭蕉という人物の偉大さを、人はそれぞれに受けとめうる。それに反して蕪村の句は、一句ずつ切り離しても、あるいは夏月、薫風、雲の峰などの季題ごとに分けて読んでも、年代順に見るのと同じ感銘を味わうことができる。」(ドナルト・キーン)
蕪村の句を味わうことの第一歩は、蕪村がその句を作った時の状況に自分を置いてみることである。ただ、それだけの所作で、蕪村の句境というのが伝わってくる。「鐘の音がする。その鐘の音を聞いていると、その鐘の音が、段々と小さくなっていく。その音の波紋、それは涼しい夏の朝の空気の波紋を暗示している。」
この句の主題は、上五の「涼しさや」にあるのだろう。
10 離別(さら)れたる身を踏込(ふんごん)で田植哉 蕪村
The divorced woman
Plunges into the paddies・・
It’s rice-planting time.
「夫に去られた女が、自分の感情を押し殺して泥田の中につかり、苦しい労働に耐えて
いる。村のつきあいとはいえ、前夫の田植を手伝わねばならない気持。蕪村は同情をあわれな女に注いでいる。なんの注釈を加えられなくとも、あわれな情景は十分に表現されている。」(ドナルト・キーン)
森本哲郎著『月は東に 蕪村の夢漱石の幻』で漱石の次の一句が披露されている。
忘れしか知らぬ顔して畠打つ 漱石
11 鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分哉 蕪村
To the Toba Palace
Five or six horsemen gallop
In the autumn wind.
「とりたてて特定の史実を想定しての句ではなかろう。騎馬武者が五六騎、野分をおし
て鳥羽殿へいそいでゆく。彼らが疾駆し去ったあとも疾風はなお吹きつのっている。中世の、物語を孕んだ一情景である。」(ドナルト・キーン)
蕪村の、大きく全体の構図を一筆で描く技法である。保元の乱の中世の絵巻物を描くつ
もりで一句に仕立てているのだろう。「五六騎」という具体性を帯びさせるための技法も、蕪村特有の描写である。
12 御手討の夫婦なりしを替衣(ころもがへ) 蕪村
They should have been killed,
But became husband and wife,
And now change their clothes.
「お手討になるところだった、というのだから、何かの罪を犯したにちがいない。どん
な罪だったのであろうか。公金を使いこんでしまったのか、それとも不義を働いたのか。たぶん、お家の御法度である不義によって、お手討になるべきところを、特別のはからいで一命を助けられ、追放ですんだのであろう。そのような過去を持つ男女が、いまは夫婦になってひっそりと暮らしている、というのである。ぼくは、この句をそう解する。折りしも、衣がえの季節。さっぱりとした衣に着がえて、身も心も軽くなった気持ちずする。出世の望みは絶たれ、暮らしもけっして楽ではあるまい。その上、この二人には、お手討になりかけたという暗い過去がある。だが、その過去のゆえに、二人はいっそう強い愛情の絆で結ばれている。苦しくても、愛情がそれをつぐなって余りあろう。二人はことあるごとに、それを確認し合いながら生きている。衣がえが、さらに蘇生の喜びを二人に、しみじみと感じさせたことであろう。わずか十七字のなかに、こうした人生のドラマを、さりげなく盛りこんだ俳人ぶそん力倆には、ただ感嘆するほかはない。『御手討の夫婦なりしを』・・これだけで蕪村は一編の小説を書いたのだ。しかも、この“小説”は読者に想像の自由を許している。二人の身の上をどのように思い描こうと、それは鑑賞者の自由である。そして、その自由を駆使して、じっさいに一編の小説をつくりあげたのが、明治の作家、夏目漱石だった。漱石の作品『門』が、それである。」(森本哲郎・『月は東に 蕪村の夢漱石の幻』)
この句の主題も、下五の「衣替」という季題にある。蕪村の作句姿勢は、この「季題中心」にある。
13 さしぬきを足でぬぐ夜や朧月 蕪村
This night the young noble
Kicks off this trouser-skirts
Under the misty moon.
「王朝の貴公子は、おぼろ月を踏んでわが宿に帰った。きっと、だれか女人を訪ねてき
たのであろう。倦怠・・あるいは微醺のせいか、指貫を脱ぐのももの倦い。じだらくに足で脱ぎ棄てられた衣は、床の上に落ちている。この浪漫的な調子は、芭蕉の句にはないものである。芭蕉も蕪村も、俳句が題材とすべきものの限界については、それぞれに確固たる認識を持っていた。だが、蕪村にとっては、俗を去ることは、必ずしも浪漫の情を避けることとは同義ではなかったのである。」(ドナルト・キーン)
平安朝の絵巻物の一つか。「朧月」からして、『源氏物語』の朧月夜の濡れ場の一情景かも知れない。自堕落な物憂い動作のも、蕪村の句作りの一つである。
14 愁ひつゝ岡にのぼれば花いばら 蕪村
Prey to melancholy,
I climbed the hill and found
Briar roses in bloom.
愁ひ来て 丘にのぼれば
名も知らぬ 鳥 啄(ついば)めり
赤き 茨(ばら)の實 啄木
蕪村から百五十年後の、石川啄木の『一握の砂』の歌である。「『愁ひつゝ』という言葉に、無限の詩情がふくまれている。無論現実的の憂愁ではなく、青空に漂う雲のような、または何かの旅愁のような、遠い眺望への視野を持った、心の茫漠とした愁である。そして野道の丘に咲いた、花茨の白く可憐な野性の姿が、主観の情愁に対象されている。西洋詩に見るような詩境である。気宇が大きく、しかも無限の抒情味に溢れている。」 (萩原朔太郎・『郷愁の詩人 与謝蕪村』)
蕪村(1716~1783)は、摂津国東成郡毛馬村(大阪市都島区)の生まれ、若いころ江戸で過ごし、さらに、結城・下館・宇都宮を始め芭蕉の『おくの細道』行脚を決行し、かれこれ十年にわたる東国を放浪したあと、京都に定住し、画家として名を馳せていた。俳諧においては、芭蕉の風を慕い、その復興を志し、そして、印象鮮明な情感豊かな独自の世界を切り開いた。師の早野巴人(宋阿)の夜半亭を継ぎ、中興俳諧運動の中心的な存在でもあった。『芭蕉翁付合集』(1776年刊行)、『夜半楽』(1777年刊)、『花鳥扁』(1782年刊)などの編著があり、没後には、几菫編『蕪村句集』(1784年刊)、句文集『新花摘』(1797年刊)などが刊行されている。
15 夕風や水青鷺の脛をうつ 蕪村
The evening breezes,
And water splashes against
The blue heron’s shins.
「一見すると、情景を客観的に描写しただけという印象を与える句である。暑い一日も
ようやく暮れようとする一刻、微風が立って水面にさざ波ができ、それが鷺の足をうっている。だが、その鷺とその脛は、たとえ間接的であっても、漢詩的なイメージを持った詞である。また、蕪村は1777年に書いた手紙の中で、上五の『夕風や』が、特別に『たけ高く清雅なる』調子を句に与えているのだと説明している。深まりゆくたそがれの中で、鷺は身じろぎ一つせず、帝王のように立ちつくしているのである。」(ドナルト・キーン)
中興俳諧の流れというのは、蕪村一人の句業の展開を見ていけば、ほぼ十分なのであるが、しかし、「芭蕉に帰れ」と芭蕉に目を向けた有力俳人が、この蕪村と同時代に期せずして輩出したのであった。
炭太祇( たいぎ・1 7 0 9 ~ 1 7 9 1 )、大島蓼太( りょうた・1 7 1 8 ~ 1 7 8 7 )、高桑闌更( らんこう・1 7 2 6 ~ 1 7 9 8 )、三浦樗良(ちょうら・1729~1780)、加藤曉臺( きょうたい・1 7 3 2 ~ 1 7 9 2 )、加舎白雄( しらお・1 7 3 8 ~ 1 7 9 1 )らであった。
これらの中興俳諧期の傑出した俳人達の活動は、芭蕉がその足跡と門弟を残した地域を中心に、全国各地に及んでいた。彼らは、江戸なり美濃、加賀なりに、それぞれの門弟を有していたが、俳諧中興の最大の拠点は、蕪村、太祇、闌更、曉臺らの居を構えていた京都であった。そして、これらの俳人の中での最長老は、太祇であった。
16 橋落ちて人岸にあり夏の月 太祇
The bridge has fallen,
And people stand on the banks
Under the summer moon.
太祇は、江戸の生まれで、江戸座の雰囲気の中で俳諧に身を染めていった。
稲津祇空(ぎくう)に師事した慶紀逸(きいつ)の門に入り、その太祇の号は、その私淑した祇空に由来があるのだろう。そして、その祇空は、『五色墨(ごしきずみ)』の連衆を指導して蕉風復帰を助長したことで知られている人である。その号の由来は、連歌師・宗祇にあるのであろう。
また、紀逸も高点付句集『武玉川(むたまがわ)』初編を出版した俳人で、川柳への道筋を開いた一人でもあるが、一方、『芭蕉翁行状記』を復刻するなど、蕉風俳諧の良き理解者でもあった。
太祇のこのような師筋からいっても、太祇は、人事趣味を得意とし技巧的な趣向の面白さをその句風としているが、蕉風俳諧にも極めて近い俳人でもあった。この句も、複雑な情景を巧みに描写して、その寸景の中に自然の荒々しさとやさしさをあざやかに集約して、その緻密な写生眼は見応えがある。
17 ふりむけば灯とぼす關(かん)や夕霞 太祇
I look behind me:
At the barrier,a light
In the evening mist.
蕪村が京に移住したのは、1751年の頃であるが、ほぼ時を同じくして太祇も京に移り住んだ。時に、蕪村は三十六歳、太祇は四十三歳の頃であった。太祇は、島原遊廓の妓楼桔梗屋の主人呑獅(どんし)の援助を得て、その遊廓の中の不夜庵に移り住む。ここで、妓楼の連衆に俳諧の指導をするとともに、手習師匠のような役をしていたのであろうか。
この句は、その頃の島原遊廓の寸景であろう。その不夜庵の主になっても、歌酒に溺れることなく、つねに風雅の俳諧の中に身を持していた太祇が彷彿としてくる。
18 寝よといふ寝ざめの夫(つま)の小夜砧(さよぎぬた) 太祇
“Let’s get to bed”says
The husband who’s been wakened:
Fulling-block at night.
太祇は、蕪村を中心とする京都俳壇の俳諧中興運動の高まりに乗じながらも、その中途にあって世を去っている。太祇が蕪村一派の三菓社に参加した頃は、1776年の頃で、蕪村五十一歳、太祇はすでに五十八歳の晩年でもあった。しかし、この両者の出会いは、その両者の俳諧の質を自ずから高めるという結果を生み出すのであった。
蕪村はゆたかな詩情をほしいままにし、非現実の美しい白日夢を演出した類稀なる俳人
であった。それに比して、太祇はつねに日常の身辺の些事の俗情に則して、その俗情にひそむ美の機微を探り当てようとした、これまた類稀なる俳人であった。
この太祇の句は、十七字の中に一つの物語を盛り込み得たという点で、蕪村の絵巻物の句とは別な観点で、その類似性とその感性の密度の濃さを教示している。
19 初恋や灯籠によする顔と顔 太祇
First love!
They draw close to the lantern,
Face next to face.
燃立(もえたち)て貌(かほ)はづかしき蚊やり哉 蕪村
この蕪村の句は、明らかに太祇の句を意識している句であろう。蕪村の句を一句一句吟
味していくと、多くのことを太祇から学んでいることが伺える。太祇の心情の襞を感性で内観する句作りは、その素直な句境の広さと深さは、蕪村に優越するものが感知される。蕪村の本性というものは、ともすると耽美主義・貴族主義の傾向が強いのであるが、太祇は、その蕪村とは正反対に俗情を愛しつつ、その俗情のままの市井趣味に徹した俳人でもあった。この点で、蕪村は太祇を常に兄事ていたことも、蕪村と太祇の交友関係から伺えるのである。
20 山吹や葉に花に葉に花に葉に 太祇
Kerria roses!
Leaves and flowers and leaves
and
Flowers and leaves and ・・
太祇の名人芸である。太祇は、しばしば、この種の同語反復や並列句による機知的な句作りを試みている。咲きこぼれる山吹の花を詠んで、あざやかな効果を上げている一句と解せられる。『太祇句選』の序で、蕪村は太祇について「かりにおこたりすさむべからずとて、仏を拝むにもほ句し、神にぬかずくにも発句せり」と記している。凄まじい俳諧修行の日常三昧であったのである。太祇の句からは、その推敲苦心の跡は些かも詠み取れないが、その作句姿勢は沈吟推敲の限りを尽くしたという。 蕪村は、この太祇に絶大な信頼を置いていた。その俳詩『春風馬堤曲』の結句に、太祇の句を引用している。
藪入りの寝るやひとりの親の側 (太祇)
21 五月雨やある夜ひそかに松の月 蓼太
All the rains of June:
and one evening,secretly,
through the pines,the moon.
この訳は、ドナルド・キーンの訳ではなく、ハロルド・ヘンダーソンの訳とのことである。嵐雪の流れを汲む雪中庵二世吏登に師事し、後に、雪中庵三世を継承することとなる。『藤衣』によれば、蓼太門には、文台を許す者四十余人、門人二千余人、編集二百有余部という。蓼太こそ、その時代にあって、俳諧中興期の第一人者として名を馳せていた中心人物であった。
蕪村の俳風が、高踏的・孤高的な一面を有していたことに対比して、蓼太の俳風は、平明さと通俗性を持ち、連句を得意としていた。このことからか、明治になって、正岡子規が『俳人蕪村』を著すまでは、俳人・蕪村は影を潜め、この蓼太こそが、当時の俳諧の寵児であったのである。
これらの一旦中興期を経た俳諧も、1783年の蕪村の死とともに、たちまち、その終焉を迎えていった。夜半亭二世・蕪村の没後、その夜半亭を継承した高井几菫(きとう)が、1789年、四十八歳でに亡くなると、その夜半亭一門の俳諧は後継者を失ったのである。
信州上田の出身の江戸で春秋庵を開いた白雄も1791年に没した。名古屋俳壇の雄であった曉台も、その翌年の1792に亡くなった。この曉台が蕪村に始めて出会った1774年の頃が、丁度、この中興俳諧運動の頂点であったのかも知れない。この時の、蕪村門と曉台門の歌仙が今に残されている。
また、中興の俳壇を蕪村と二分し、その東を代表した当時の俳諧の寵児・蓼太も、1 787年に、七十歳の生涯を閉じた。こうして、俳諧の中興期は終わりを告げたのである。
ドナルド・キーンの『俳諧入門』(その八)
第9 徳川後期の俳諧
1793年は、芭蕉の百回忌に当たり、全国各地で追悼会が営まれ、諸所で句碑が建てられ、芭蕉作品の復刻や注釈書がしきりに刊行された。俳諧の宗匠達は、競って、芭蕉崇敬熱にあやからんと『おくの細道』行脚を決行し、このみちのくの行脚は、俳諧宗匠の資格を得るための必須のものとまで異常な高まりを見せるのである。
同時に、ますます、芭蕉の神聖化は進み、1843年の芭蕉百五十回忌には、柿本人麿と並ぶ最高位の神号「花の本大明神」さえ与えられるのである。
このような現象と併せ、俳諧の大衆化はますます進み、それは社交遊楽に不可欠な社会的技術と目されるまでに至るのである。このことは、必然的に俳諧の芸術的水準の低下をもたらし、もはや厳しい詩精神などとは裏腹のものへと変遷を遂げていく。このような芭蕉の精神とは正反対の卑俗平明な俳諧へと堕していくのであるが、表面では芭蕉崇拝を唱え、季語、切れ字、その他表面的、形式的な約束は、それを遵守して疑うことがなかった。
かっての俳諧愛好者が、それを風雅の友とすることで満足していたのと違って、彼等は自分達の作品と名が公刊されることをあくまで求めるようになったのである。
1 寝起(ねおき)から団扇(うちは)とりけり老にけり 道彦
As soon as I get up
I take my round fan in hand------
How old I’ve become!
1790年代(寛政期)を代表する鈴木道彦(1751~1819)の句である。道彦は、仙台の人で白雄門である。道彦は芭蕉を絶対化し、芭蕉の風雅の旅装をなぞり、ついには自分を蕉門の十哲に擬するほどの傾倒ぶりを見せるのである。
「夏の午後、昼寝から醒めた老人は、手をのばして団扇をとる。そのときに襲ったけだるさの中に己の老齢を知る。『けり』の繰り返しが、だるい気持を効果的に強めている。」(ドナルド・キーン)
2 さびしさや火を焚く家のかきつばた 道彦
What lonliness------
Irises beside a house
At fire-lighting.
「“や”という切れ字も、かきつばたという季語も、そこにはそろっている。句そのものも、芭蕉と同じ閑寂の境地を狙っている。だが、それはほんとうに寂しくあるためには、かきつばたは、あまり適切な選択とは言えないのである。」(ドナルド・キーン)
後年、道彦は蕉風の歪曲者として指弾されることとなるが、芭蕉の理想の帰一を願い、
同時に、俳諧の大衆化に努めた道彦もまた、その時代の申し子だったといえるのかも知れない。
3 はや秋の柳をすかすあさ日かな 成美
Autumn・・already
The morning sun pierces through
The willow leaves.
19世紀の初頭(文化文政期)、特定の派に属さない作家が輩出されるようになる。その代表的な俳人として、夏目成美(1749~1816)が上げられる。浅草蔵前の裕福な札差だった彼は、道彦一派に代表される職業俳諧(業俳)に反発し、俳諧は生活の糧ではなく、余技にする遊俳たるべしという立場であった。
また、成美は江戸流寓中の一茶を物心両面にわたり援助し、一茶をして名をなさしめた陰の庇護者としても名高い俳人である。
この句は、都会人的な繊細な感性を句風とする成美をいかんなく表出している句といえるであろう。
4 有明や浅間の霧が膳をはふ 一茶
At break of dawn
The fog from Asama creeps
Over my breakfast tray.
「浅間の見える軽井沢の朝が、みごとに叙景されている。冷え冷えとする秋のあかつき、朝立ちの旅人の前の膳に霧が這い寄る。まだ空に残る月が鈍い光を落としているのかもしれない。1812年のこの作、成美や乙二が継承した中興俳諧の伝統を、一茶もまた継ごうとさえ思えば継ぎえたことを例証している。」(ドナルド・キーン)
この時代にあって、今日なお芭蕉や蕪村に匹敵し得るほどの人気を保っている俳人として小林一茶(1763~1827)が上げられる。一茶の師匠は、葛飾派の俳人二六庵竹阿であった。その師の竹阿の死とともに若干二十七歳で一門を一茶が率いるようになったのも、すでにその頃から天賦の才能が認められていたかの証左であろう。
一茶は、芭蕉・蕪村と並んで江戸期の三大俳人に列せられるが、この三人の俳風は、「芭蕉のストイシズム、蕪村のロマンシズム、一茶のニヒリズム」あるいは「芭蕉の句が自然をかりての精神の象徴であるとするならば、蕪村の句は絵画的な方法をかりての自然の再現であり、一茶の句は、彼の心情の素直な表明であるとすることができよう」などといわれている(松尾靖秋・『近世俳人』)。
しかし、一茶は、芭蕉・蕪村が代表する伝統的俳諧に比して、俗語調・浮世風の異端の俳諧に位置する俳人でもある。また、芭蕉・蕪村の俳諧が、その時代の新風の代表ないしは中心として認められるのに比して、一茶の俳諧は、その強烈な個性と特異な小さいものの観察などによる独特の俳風が、それまでの俳諧史上稀であるという偶然性により、そのことが、三大俳人の一人に選ばれている理由とも思われ、前二者とは同列に論じられないものがある。 その一茶も、この句のドナルド・キーンの評にあるごとく、夏目成美や岩間乙二(1756~1823)の蕪村調の耽美的・浪漫的な俳風の一面を有しているのである。
すなわち、一茶は、言語遊戯的な葛飾派で育ったが、成美や乙二と同じように、その葛飾派とは正反対の、蕪村を中心とする天明俳諧への憧れと、そのための俳諧修業を経ているということである。
5 夕風や社(やしろ)の氷柱(つらら)灯の映る 一茶
The evening winds------
Lamplight from inside the shrine
Reflects on icicles.
この一茶の句は、その師・竹阿の死亡後、葛飾派を脱し、1792年に上方、四国、九州行脚にでかけた頃の作である。この句作りは、蕪村らを中心とする天明俳諧の耽美的・高踏的なそれで、後の現実生活中心の現実主義とユーモラスな俳風の一茶調の片鱗も伺えない。
この時の彷徨は、1798年の頃まで続いた。この七年にわたる旅は、後の一茶調を生みだす素地になっているのだが、これに続く十四年間の江戸での一俳諧師としての生活は貧窮を極めていた。彼は、しばしば自嘲をこめて己自身を「乞食一茶」と書いている。
6 露の世は露の世ながらさりながら 一茶
The world of dew
Is a world of dew,and yet,
And yet.
長い離郷の後に故郷信濃に帰ったのは1801年のことであった。一茶の父は死の床についていた。その夏、父親が息をひきとるまでの一ヶ月を看病に捧げた。この間のことについては『父の終焉日記』に詳しい。
この時の父の遺言をめぐって、継母と弟との間の遺産争いが1813年まで続く。その
骨肉の争いも和解し、幾ばくかの不動産を得た一茶は、ここを終の住処とする。五十歳を越して妻を娶るのだが、その妻との四人の子は次々と亡くなり、その妻まで亡くなってしまう。
この句は、当時の亡くなった子を悼んでの一句で、その『おらが春』編中の最も悲痛な場面でもある。
7 我を見て苦い顔する蛙かな 一茶
When he looks at me
What a sour face he makes,
That frog over there!
8 痩蛙まけるな一茶是に有り 一茶
Skinny frog
Don’t get discouraged:
Issa is here.
作家としての一茶の生涯で、最も充実していた時期は1801年の父の死から1818年の長女誕生の頃で、特に、その後半の八年で、実に七千三百句が書かれている。古歌のもじり、先人の模倣、川柳とほとんど変わらないような句をはじめ、俗語、方言、俗謡を駆使し、きわめて多彩な句風を展開している。
芭蕉の蛙は「古池や蛙飛び込む水の音」と風雅な閑寂趣味の蛙であるが、一茶の蛙は、生活の痛苦と華やかな世相の裏側に隠された人生の惨苦と矛盾を風刺する蛙であった。・の蛙は、骨肉の争いを展開した継母と弟の分身かも知れない。・の蛙は、四十を過ぎても妻帯のできない一茶を嘲り笑っている者に対する一茶の挑戦かも知れない。
いずれにしろ、ここには、一茶だけが可能であった俳諧の世界がある。
9 我と来て遊べや親のない雀 一茶
Come with me,
Let’s play together,sparrow
Without a mother.
『おらが春』では「六歳 弥太郎」とあり、一茶が六歳の時に、この句の原形があると
いう。この句の初出は「七番日記」で、「我と来てあそぶ親のない雀」の形で入集されている。
一茶は三歳で母と死別し、祖母の手で育てられたが、八歳の時に継母を迎え、それより継子として不幸な日々が始まった。いずれにしても、この句は、その頃の幼時の追憶吟であろう。
10 やれ打つな蠅が手を摺り足をする 一茶
Hey!don’t swat him!
The fly rubs his hands,
rubs his feet
Begging for mercy.
この句は、『文政日記』の1821年の一茶五十九歳の時の作である。その前の年に、中風で倒れるが、その時は軽症で、それから三年後に中風が再発し、言語障害を起こす。一茶の生涯というのは誠に不遇の一語に尽きる。幼児に母を亡くし、その前半生は乞食のような放浪の生活と継母との骨肉の争い、そして、その後半生は、最初の妻との死別、その妻との間の四男一女もことごとく死別、二度目の妻とは離別、そして、三度目の妻とは、遺児のみを残して中風の発作で六十五年の生涯を閉じると、実に薄幸な数奇な運命を享受した。
一茶の句は、この薄幸な数奇な運命の裏返しで、この川柳とも思われる句の蠅も、一茶の分身のように思われるのである。
11 世がよくばも一つ泊まれ飯の蠅 一茶
If the times were good,
I’d say:“One more of you,
sit down,
fries around my food.
この訳は、ハロルド・ヘンダーソンのものである。「ぼうふら、蜘蛛の子、そのほか普通なら嫌悪の対象になるはずの虫の小動物にまで、一茶は共感の情を注ぐ。そのような句は、たしかに面白い。しかし、蛙や蠅やかたつむりへの感情移入が真に俳句と呼ばれるべきかどうかは、疑問の余地のあるところであろう。そこには、ほとんど緊張がなく、読む人の心に緊張を喚起する強さもない。俳句の形をとった警句(エピグラム)の域をさほど出るものではありえない。」(ドナルド・キーン)
このドナルド・キーンの一茶評は、ある意味で酷であるという印象を脱ぐえない。一茶は、自分の絶ち難い我執、執拗な利己性そして気弱な善人性などの、その自嘲と極端な愛憎の交錯が、蠅やぼうふらや蜘蛛の子なとの小動物への感情移入となって表れているのである。
所詮、一茶の俳諧は、一茶一人だけのものなのである。それは学ぶべきものでも、また伝え得る俳諧でもないのだ。いはば、俳諧史に狂い咲いた野性の突然変種で、芭蕉・蕪村と続く俳諧の流れとは異質のものなのである。
「一茶には後継者が現われなかった。彼という存在がなくとも、俳諧史にはあまり変化がなかったかもしれない。しかしまた、われわれは一茶を得たことを喜びとするべきであろう。彼の句からにじみ出る真心と人間的な暖かみは、俳諧史の中ではやはり特異のものであり、それ自体として傑出したものだったからである。」(ドナルド・キーン)
一茶が彗星のようにその特異な存在を俳諧史上に示した後、文政の末年から天保の時代
に入ると、ますます俳諧の大衆化は加速をつけていく。その通俗性はもはや救うべからざるものとなってしまったのである。
「明治時代になって、正岡子規は1 8 3 0 年代( 天保期) の俳人達を『月並調』と呼んではげしく批判した。月並は月例の句会の句風で、陳腐な兼題、席題を与えられた人々が実際の写生や感情にはなんの関係もなしに出す作を指している。たしかに、そのような俳句には俳諧の花であね『新しみ』が欠け、今日読み返してみてもなんの感動も与えないものが多い。俳句は生け花と同様、全国の大衆の手すさびになってしまったのである。隠居した老人や有閑女性に喜ばれる遊びにはなったが、もはや人間深奥の感情を伝える詩ではなくなった。現代に至って俳句第二芸術論が起こったことからも知られるように、つくって出版するには楽しいかもしれないが、心をこめて読むほどの価値は失われてしまったのである。」(ドナルド・キーン)
この徳川の最後期の天保俳壇の代表作家は、田川鳳朗(ほうろう・1762~1845)、桜井梅室(ばいしつ・1769~1852)らであった。
彼等は、後に正岡子規によって最大の攻撃目標とされた。その句が「月並調」であり、本物の経験や観察に欠け技巧と言いまわしだけのものとして批判されるのである。
冬の日もまだ白菊の明りかな 鳳朗
椿落ち鶏鳴き椿また落つる 梅室
しかし、彼等もまた時代の申し子であった。彼等は、芭蕉・蕪村の開花したままにその俳諧を享受した。そして、その落花を防ぐべく手立ても方策もを知らなかったのである。
「天保俳壇は、遠く芭蕉を顧み、芭蕉によって樹立された俳諧の嫡子たらんとした。ただ、その時期に生きた詩人たちは、芭蕉がとなえた『流行』を忘れ、変化が真の永遠なるものにとっては不可欠であるという事実を、悟ることがなかったのである。」(ドナルド・キーン)
土曜日, 10月 20, 2012
曽良と『曽良旅日記』
曽良と『曽良旅日記』
河合曽良(かわいそら)とは謎の満ちた俳人である。その名は、芭蕉の『おくのほそ道』の随行者として、その俳人の名以上に知られている。
曽良は慶安二年(一六九四)に信濃国上諏訪(現長野県諏訪市上諏訪町)に生まれ、宝永七年(一七一〇)五月二十二日に壱岐国勝本(現長崎県壱岐郡勝本町)で病没した。時に六十二歳であった。 曽良と芭蕉との年齢差は僅かに五歳ということであり、芭蕉自身の記述においても両者の親密さの度合いを推量することができる。その『おくのほそ道』の「日光」の章で、曽良の「剃捨(そりすて)て黒髪山に衣替(ころもがへ)」の句を紹介しながら、芭蕉は、曽良について、次のように記述している。
「曽良は河合氏(かはひうぢ)にして惣五郎(そうごろう)と云へり。芭蕉の下葉(したは)に軒をならべて、予が薪水(しんすい)の労をたすく。このたび松しま・象潟(きさがた)の眺(ながめ)共にせん事を悦び、且(かつ)は羈旅(きりよ)の難をいたはらんと、旅立(たびたつ)暁、髪を剃(そり)て墨染(すみぞめ)にさまをかえ(へ)、惣五を改(あらた)めて宗悟(そうご)とす。仍(よつ)て黒髪山の句有(あり)。衣替の二字力ありてきこゆ。」
芭蕉と曽良との出合いは、天和三年(一六八九)の、曽良三十五歳の時とされ、貞享二年(一六八五)、芭蕉庵の近くの、深川五間堀を本拠とし、芭蕉の日常生活に何くれと奔走したのであろう。 その貞享四年の秋の鹿島詣でにも、宗波(そうは)と共に芭蕉に随行している。
芭蕉が、奥の細道の長旅を始め、二度も曽良を随行者としているのは、曽良が、その神道・地理・国学・和歌などに造詣が深かったということも、その一因として上げられるであろう。曽良は、神道を吉川惟足(これたる)に学び、この吉川惟足門にいて、これらの造詣を深くしたと思われる。 曽良は、後の宝永六年(一七〇九)に、将軍の代替わりにともなって諸国を巡査使が派遣された際には、土屋喬直(たかなお)の用人として随員に加えられており、いわば、旅や地方の実情などに関して職業的にも精通した人であったということができるのかも知れない。
とにもかくにも、旅に生き旅に死んだ俳聖・芭蕉の、その不朽の名作『おくのほそ道』の、その旅の随行者として、曽良は、元禄二年(一六八九)・同四年次の『曽良旅日記』を、今に残しており、これは、当時の芭蕉の動静を記録したものとしても、いや、それ以上に、俳聖・芭蕉の全体像を把握する上からしても、大変に貴重なものであり、芭蕉と、その『おくのほそ道』が、その名を止めている限りにおいて、芭蕉の随行者としての、曽良の名も永遠に記録され続けることであろう。
〔俳人としての曽良〕
○ なつかしや奈良の隣の一時雨(伊賀の堺にて)
○ 浦風や巴をくづすむら鵆(ちどり)
○ 畳め(目)は我が手のあとぞ紙衾(かみぶすま)(題竹戸之衾)
○ 松嶋や鶴に身をかれほとゝぎす(松嶋一見の時、千鳥もかるや鶴の毛皮とよめりければ)
○ 破垣(やれがき)やわざと鹿子(かのこ)のかよひ道
○ 月鉾や兒(ちご)の額の薄粧(うすけはひ)
○ 終夜(よもすがら)秋風きくや裏の山(加賀の全昌寺に宿す)
○ いずくにかたふれ臥(ふす)とも萩の原
(元禄二年翁に供せられて、みちのくより三越路にかゝり行脚しけるに、かゞの国にていたはり侍りて、いせ まで先達(さきだち)けるとて)
○ 向(むき)の能(よ)き宿も月見る契(ちぎり)かな
○ むつかしき拍手も見えず里神楽
○ 大峯やよしのゝ奥の花の果
(はなも奥有(あり)とや、よしの深く吟じ入(いり)て)
○ 春の夜はたれか初瀬の堂籠(ごもり)
○ 涼しさや此庵をさへ住捨(すみすて)し(明年夏尋旧庵)
芭蕉俳諧の最高峰を示すものとして名高い『猿蓑』(凡兆・去来編)に入集されている曽良の十三句である。この『猿蓑』には三八二句の俳句(発句)が入集されているが、その入集の多い順でいくと、凡兆(四一句)、芭蕉(四〇句)、去来・其角(二五句)、尚白(一四句)、史邦(一三句)、丈草・羽紅・曽良(一二句)の順で、江戸在住の蕉門では、其角に次ぎ、嵐雪・杉風(五句)より上位を占めている。
この当時、俳人としての曽良の絶頂期であったのだろう。この『猿蓑』は元禄三年から四月にかけて編纂されたもので、正に、芭蕉と曽良との『おくのほそ道』の旅(元禄二年)の、その直ぐ後に刊行されたものである。いや、それ以上に、この『猿蓑』が編纂されていた頃、曽良も京におり、この『猿蓑』の編纂の一躍を担っていたとも思われる記事と当時の芭蕉の状況などが、その『曽良旅日記』(「曽良元禄四年近畿巡遊日記」)に記されている。
○廿六日(元禄四年旧暦五月)、雨天、集ノ義取立(トリタテ)深更(シンコフ)ニ及(オヨブ)。○八日未明(元禄四年旧暦六月)、翁(芭蕉)病気甚シ、吐瀉有(アリ)、終日不慥。昼時北野へ行テ、長者町ヘ帰テ、又、小川ヘ行テ宿。
○九日(天晴)、今日叡山ヘ行クベキノ所翁(芭蕉)病気故止(ヤム)。夜前、乙州来テ宿ス。丈草来テ同道、凉ヲ見テ中村ニ宿ス。
この記事に関連して、芭蕉が湖南の幻住庵に入ったのは、元禄三年の四月初旬であり、当時の曽良が芭蕉に宛てた同年九月二十六日付け書簡などによると、曽良は芭蕉の病状を深く憂え、ことあれば江戸の深川庵に帰るよう催促しており、その芭蕉を迎えるための頃の曽良の記録とも受け取れるのである。
芭蕉も、この曽良の江戸への帰庵の催促に応じたのか、その元禄四年七月の『猿蓑』の刊行を見て後、その年の九月に義仲寺無名庵を発って帰東の途に着いている。そして、芭蕉が、支考と桃隣との同道にて江戸に帰着したのは、その年の十月のことであった。
これらのことを見ていくと、当時の曽良は、江戸の蕉門の実質的な芭蕉の代役という感じで、その連句・発句の両面において、当時の芭蕉の俳境を、身近かにあって一番吸収した俳人であったということがいえそうである。
しかし、曽良の俳諧(連句・発句)におけるその句作の全貌というのは、蕉門十哲といわれる他の俳人に比して、極めて少なく(百三・四十句)、その句作りの表現趣向においても理知的傾向が強いともいわれ、蕉門十哲としての曽良の名を見出すことはできない。
ともあれ、俳人としての曽良は、芭蕉俳諧の最高峰の二つの、『猿蓑』と『おくのほそ道』の、両方にその名を止め、芭蕉の名と共に、その影のごとくにして、その俳諧史上その名を止める俳人であることは疑う余地のないところであろう。
〔『曽良旅日記』〕
『曽良旅日記』は、『曽良随行日記』ともいわれ、元禄二年(一六八九)と同四年との旅の日記的な曽良の自筆メモというのが、その内容である。そして、それは、次の六部より構成されている。
① 「延喜式神名帳抄録」
『おくのほそ道』の旅で芭蕉に随行するに際して、予め通過予定の土地の神社名を、『延喜式』神名帳から書き抜いたものである。
② 「歌枕覚書」(「奥の細道名勝備忘録」)
「延喜式神名帳抄録」と同じく、通過予定の各地の歌枕を列挙したもので、その資料は『類字名所和歌集』と『楢山拾葉(ならやましゆうよう)』に拠るとされ、さらに、現地踏査で得たものを、後で行間余白などに書き込んでいる。
③ 「元禄二年日記」(「奥羽の旅日記」・「曽良奥の細道随行日記」)
元禄二年三月二十日から同年十一月十三日までの旅に関する日記。芭蕉の『おくのほそ道』の旅の基本的な記録で、芭蕉の不朽の名作『おくのほそ道』を理解する上において必須の資料といえる。
④ 「元禄四年日記」(「近畿巡遊日記」・「曽良元禄四年近畿巡遊日記」) 元禄四年三月四日から七月二十五日までの旅に関する日記。『猿蓑』編纂時の芭蕉やその周辺の蕉門の俳人の動静と俳人曽良を理解する上で貴重な資料といえる。
⑤ 「俳諧書留」(「奥の細道俳諧書留」)
『おくのほそ道』の旅で各地で作られた自(曽良)他(芭蕉等)の発句・連句・文章などを日記とは別に記録したもので、各作品の初案形などを知る上で必須の資料といえる。
⑥ 「雑録」(「弓道覚書・貞室逸話などの種々の雑録」)
『おくのほそ道』の旅で山中温泉で聞いた貞室逸話や二度の旅日記に関連する人名・住所録・古歌などが記録されている。
これらの、『曽良旅日記』が現存することは江戸時代においても一部には知られていたが、その全貌が明らかにされたのは、昭和十八年七月の、山本安三郎(俳号・六丁子)編『曽良奥の細道随行日記・附元禄四年日記』(小川書房)によってであった。さらに、杉浦正一郎校注『芭蕉おくのほそ道・附曽良随行日記』(岩波文庫)によって、広く一般の人にも流布され、それが、現在の、萩原恭男校注『芭蕉おくのほそ道・付曽良旅日記』((岩波文庫)や潁原退蔵・尾形仂訳注『新訂おくのほそ道・附曽良随行日記』(角川日本古典文庫)によって引き継がれているのである。
なお、この『曽良旅日記』の原本は、潁原退蔵・尾形仂訳注『新訂おくのほそ道』によると、「古美術の収集をもって聞こえた斎藤幾太氏が明治年間に大阪で入手したもので、戦後斎藤浩介氏より杉浦正一郎博士に譲られ、--、現在は天理図書館綿屋文庫蔵に帰している」ということである。
これらのことに関して、山本安三郎編『曽良奥の細道随行日記』の「はしがき」には次のように記述されている。
「嘗(かつ)て某家に年久しく伝へられたる古名流俳家の墨蹟文書等を愛蔵せらるゝを仄聞(そくぶん)してゐた私は、昭和十三年夏同家に於ける蔵品一部の曝凉(ばくりやう)に際し、友人佐藤十雨君の紹介にて拝覧する機会を得た。--、別けても私の瞳の底に強く灼(や)きつけられた一品があつた。それは河合曽良が松尾芭蕉に随従して、奥羽北越の行脚即ち奥の細道の行脚の『旅日記』であつた。 如斯(かくのごとき)日記が今日まで完全に残されてあつたことは私の思ひもつかぬ驚異であつた。奥の細道行脚の日より約二百五十年間、芭蕉研究に於ける汗牛充棟(かんぎうじゆうたう)も啻(ただ)ならざる文書記録等にも、未だ嘗て顕(あら)はれたことの無い史料である--。」
そして、同書の「序」(志田義秀)では、「これによつて学会の蒙(かうむ)る裨益(ひえき)は蓋(けだ)し大なるものがあろう」とあり、これによって、新たな『おくのほそ道』探査が始まったともいえるであろう。
その山本安三郎編『曽良奥の細道随行日記』の内容は、「曽良奥の細道随行日記」・「奥の細道俳諧書留」・「奥の細道名勝備忘録」・「延喜式神名帳抄録」・「曽良元禄四年近畿巡遊日記」・「奥の細道随行日記異同比較考え」・「奥の細道天候と旅宿一覧表」の七部構成となっている。
しかし、本書そのものの入手が一般的には困難になってきたと共に、その著の「本書を読まるゝ方へ」にあるとおり、「仮名遣ひの相違、片仮名平仮名混用、当字誤字、脱字、抹消、書直し其他に由る難読の箇所も随處にみられ」、その校注のみでの理解は相当に困難といえるであろう。
そして、この山本安三郎編の『曽良奥の細道随行日記』に継ぐものとして、前述の、杉浦正一郎校注の「曽良随行日記」(岩波文庫『芭蕉おくのほそ道』所収)が昭和三十二年に刊行され、これが、山本安三郎編の『曽良奥の細道随行日記』にとって代わり、今日の基本的な参考文献といえるものであろう。しかし、これも、その刊行からほぼ四十年という時の経過からして、その校注などに改訂を要する部分も目につくようになり、この著も、前記の萩原恭男校注『芭蕉おくのほそ道・付曽良旅日記』や潁原退蔵・尾形仂訳注『新訂おくのほそ道・附曽良随行日記』などを併用しないと、なかなかその理解は困難を伴うものと思われるのである。
ともあれ、芭蕉の不朽の名作『おくのほそ道』の、より良き理解のために、この『曽良旅日記』の果たす役割は大なるものがあり、この意味において、もっともっと、この『曽良旅日記』関連の参考文献が多くなり、その芭蕉の『おくのほそ道』と同程度に、それらの整備充実こそ真に望まれるものと思われるのである。
更には、この『曽良旅日記』そのものだけではなく、その抄録ともいわれている、その他の諸本の踏査についても切に望まれるものと思えるのである。
〔『曽良旅日記』の抄録などの諸本〕
昭和十八年七月の山本安三郎(俳号・六丁子)編『曽良奥の細道随行日記・附元禄四年日記』(小川書房)の刊行によって、その全貌が明らかにされたところの、この『曽良旅日記』は、この抄録とも思われる諸本が、『詳考奥の細道(阿部喜三郎著)』に紹介されている。それらの諸本とその要旨は次のとおりである。
① 人見本・小山田本
下野新聞(昭和二六・六・一七)等に、「那須に伝わる曽良日記の人見本」の記事が出て、古川清彦説(「連歌俳諧研究一」)の紹介が現れた。それによると人見本とは那須湯本温泉神社の神職で旅館和泉屋を経営する人見義男蔵の一本、小山田本とは那須郡黒羽町の小山田モト子蔵の一本で、内容はともに(少しの異同はあるが)、「巳三月廿日 深川出船千住上ル廿六日迄逗留」とある冒頭から五月「十七日 尾花沢清風泊」とあるまでの随行日記の抄録である。
人見本は、その付記によると、嘉永五年(一八五二)に人見家の先祖が写したもの、小山田本には「此日記高久村覚左衛門が家に曽良正筆あり写之」とある。小山田本は旧黒羽藩郡奉行で歌人であった小山田栄重(号・稲所)の筆録した『前岡雑記』第七篇中に収められおり、郷土史家・人見伝蔵説によると、稲所が天保の中頃から弘化の初めにかけて(一八四四)の頃の郡奉行の在職中に、高久家から借覧したものであろうということである。
現在、高久家には伝存するものはないが、古川説は、これらの二本は別々に高久家から伝写されたものであろうということである。この基になっている高久家本については、松本義一説(「連歌俳諧研究七・八合併号)は、芭蕉の真蹟類を多く蔵した高久家としては、曽良筆のものもあった可能性があるとてされるが、久保忠夫説(連歌俳諧研究一四)は、「そのもとの本は曽良自筆とは考えられない」とする。この久保説によると、人見本は小山田本の写しで、更に、後述の『青かげ』・『御正伝記」を加え、これらの四本が基づいたものは一つであったろうと推測している。そして、出立時の「廿六日迄逗留」や仙台の所での「法運寺」の誤読などから、「そのもとの本は曽良自筆とは考えられない」とするのであるが、阿部喜三郎説(前掲書)は、「久保説は推測説ではあるが、ほぼ首肯できる。ただし、前記の松本・古川・人見説も可能であって、この間の事情はまだ十分には確定しがたい」としている。
② 青かげ
須賀川の雨考編の俳書で、文化十一年(一八一四)の頃の刊行である。この中に「むかし翁行脚の頃、泊々の日記といふものをもたる人ありて、写しこしぬ。今細ミちと校合するに、多くたがはず。筆者しれがたけれど、おほやう曽良がおぼえ書とみゆ。其書のうち少々左にうつし出す」として、随行日記の四月廿一日(白河)から五月九日(松島)までの記事(中略も含む)の抄録を載せている。
③ 芭蕉桃青翁御正伝記
天堂一叟の自筆稿本(天理図書館蔵)五巻(四冊)の巻一の終部に、出発より五月十七日(尾花沢・鈴木清風宅)までの随行日記の抄録が掲載されている。この抄録は、『詳考奥の細道(阿部喜三郎著)』によれば、筆者の付加したものが多いとの評価を受けている。
④ 奥の細道下露抄
筆者未詳の稿本の一冊(天理図書館蔵)で、冒頭から立石寺の句までの注釈が掲載されているが、その中に、尾花沢までの随行日記の抄録が引用されているという。『詳考奥の細道(阿部喜三郎著)』によると、この抄録は、前述の小山田本に最も近いものとされている。
⑤ 句安奇禹度(句商人)
大阪堂島の竹齋が細道の旅を志して、文化五年の冬から翌年にかけて旅をし、旅中の収得を集めて文化七年(一八一〇)に刊行した俳書で、この中で「今信州上諏訪久保嶋氏にて写す」とあり、随行日記の原本にある表紙見返しの仙台略図と九八丁表の「元禄二年七月廿日書之」の一行を透写しているという(杉浦正一郎校注『芭蕉おくのほそ道』)。
これらの、『曽良旅日記』の抄録などの諸本のうち、その「人見本・小山田本」(一部は「芭蕉桃青翁御正伝記」)について、『曽良随行日記』(岩波文庫『芭蕉おくのほそ道』所収)と併せ、『詳考奥の細道(阿部喜三郎著)』により、掲載しておくこととする。
『曽良旅日記』などに関する参考文献(本稿で参考とした文献は※印)
〔影印〕『芭蕉紀行文集』(天理図書館善本叢書一〇・八木書店・昭和四七)
〔翻刻〕※『曽良奥の細道随行日記 附元禄四年日記』(山本安三郎編・小川書房・昭和一八)
〔参考翻刻〕※『芭蕉おくのほそ道 附曽良随行日記』(杉浦正一郎校注・岩波文庫・昭和三二)
※『芭蕉おくのほそ道 付曽良旅日記』(萩原恭男校注・岩波文庫・昭和五四)
※『新訂おくのほそ道・附曽良随行日記』(潁原退蔵・尾形仂訳注・角川文庫・昭和四二)
「曽良随行日記」(『校本芭蕉全集六』・井本農一校注・角川書店・昭和三七)
〔参考資料〕「杉浦博士未翻刻・曽良日記」(『近世文芸資料と考証一』・中西啓執筆・昭和三七)
「曽良自筆『奥の細道随行日記』解説」(『芭蕉研究』・杉浦正一郎執筆・昭和三三)
「旅日記の曽良」(『芭蕉論』・上野洋三執筆・昭和六二)
『蕉門曽良の足跡』(今井黙天著・信濃民友社・昭和二八)
『河合曽良追善集収録』(今井邦治著・信濃民友社・昭和三四)
「河合曽良」(『信濃路の俳人たち』・藤岡筑邨執筆・信濃毎日新聞社・昭和五〇)
※「河合曽良」(『俳人評伝下(俳句講座三)』・久富哲雄執筆・明治書院・昭和三四)
※「随行日記〔連接資料〕等」(『『詳考奥の細道(増訂版)』・阿部喜三郎著・久富哲雄補訂・日栄社・昭和五四)
芭蕉の『おくのほそ道』二部構成論
芭蕉の『おくのほそ道』二部構成論
(一)
「橘」の「創刊一五〇号記念特集号(平成二年六月)」の招待評論の一つは、井本農一氏の「奥の細道二部構成論序説」というものであった。そこで展開されたものは、『中世の文学』・『無用者の系譜』・『中世から近世へ」・『詩とデカダンス』などの著書を有する日本文芸思潮史の研究に大きな足跡を残した唐木順三氏の「芭蕉の日本海体験」(『続あづまみちのく』所収)における「奥の細道二部構成論」の紹介とその批判的考察(その二部構成論は肯定し、それを芭蕉研究をライフワークとし、芭蕉研究第一人者である井本農一氏として、唐木順三氏とは違った観点からの二部構成論の展開)の、その序説的な評論であった。
そこでは、限られた枚数の制限上、唐木氏の二部構成論の「牽強とみずから(註・唐木順三)思う」の、連句の歌仙(三十六句からなる連句形式)と半歌仙(十六句からなる連句形式)とに関連づけての、その理由づけの難点の紹介に止まり、井本氏自身の二部構成論にまでには立ち至ってはいなかった。
そして、その書き出しは、「私(註・井本農一)はかなり前から、私なりに奥の細道の二部構成説を温めていて、--」というものであり、その井本氏の、その二部構成論というものは、どのようなものなのか、ずうと関心を持ち続けていた者の一人なのである。そして、それは、『芭蕉とその方法』(平成五年十一月・角川書店)という著書の中で「『おくのほそ道』二部構成論」・「付・『おくのほそ道』二部構成論序説」という形で、その他の関連論説と併せ公表されたのである(初出の俳誌名等については後述する)。
ちなみに、そこでの、「付・『おくのほそ道』二部構成論序説」というものは、「橘」の、その創刊一五〇号記念特集号で発表したもののその前半部にあたるものであった。そこで、紹介されている、唐木氏の前掲論説の冒頭の書き出しは次のようなものであった。「芭蕉の奥の細道の旅は事実上、象潟までで終わった。元禄二年(四十六歳)の旧暦三月二十七日、江戸を立ち、同年六月二十四日に酒田をあとにして、日本海を右に見て南下するまでのおよそ三ケ月で、この旅にかけた目的は達せられたと言ってよい。江戸出発にあたっての離別の句、『行く春や鳥啼(なき)魚の目は泪(なみだ)』を発句とし、象潟での、『象潟や雨に西施がねぶの花』を揚句とすれば、その間にちりばめられた芭蕉句二十九、曽良句七、合せて三十六句で歌仙の形になる。芭蕉がどこまでそれを意識してのことかは別として、『象潟や』はやはり奥の細道の旅の揚句であったと私(註・唐木順三)は見る。」
(二)
ここで、次に、井本農一氏の『おくのほそ道』二部構成論(『芭蕉とその方法』所収)について、その概要を記しておきたい。その冒頭の書き出しは、「『おくのほそ道』の構成については、江戸時代以来いろいろの説があり、それぞれに一理があって捨てがたい」として、いわゆる『おくのほそ道』にかかわる構成論の紹介から始まっている。その構成論の主なものは次の通りである(なお、『奥の細道』・『おくのほそ道』などの題名については、それぞれの著書のそれによる)。
A 二部構成説
唐木順三 1 象潟まで 2 酒田以後(前半は歌仙形式・後半は半歌仙形式) 久富哲雄 1 象潟まで 2 酒田以後(発句を中心にした各章を連句的手法で配列)
B 三部構成説
松井 驥 1 芦野まで 2 象潟まで 3 大垣まで(五十韻形式)
C 四部構成説
尾形 仂 1 芦野まで 2 塩釜まで 3 象潟まで
4 大垣まで(歌仙形式の「一ノ折」表・裏、「二ノ折」表・裏、全体:序・破・急の 流れ、 地(軽くやすらかな作)と文(趣向をこらした秀逸の作)の配置。井本氏 は直接は、これらのことについては言及していないので、その『新訂おくのほそ 道』での補注的私注である。)
井本氏は、これらの紹介の後で、芭蕉の奥の細道探訪の狙いを詳細に言及して、中世の後期室町時代の歌謡を集めた『閑吟集』などを基礎としながら、それは『奥羽の歌枕』探訪の旅であったとするのである。その氏の記述は次の通りである。
「奥羽の歌枕への憧憬の伝統は、近世にまで受け継がれている。伝統へ反逆する近世的な人間もいるけれども、堂上歌壇はもとより、芭蕉のような一方では近世化へ傾斜しながら一方で伝統を拠り所とする文人たちの間には、中世以来の奥羽への憧憬があった。西行崇拝はもとより、能因や宗祇への敬慕が芭蕉にあったことは言うまでもない。」
そして、この後で、氏は、元禄二年閏正月芭蕉書簡(卓袋宛て=推定)・元禄二年二月十五日付芭蕉書簡(桐葉宛て)などを根拠としながら、「芭蕉の旅の目的地は陸奥・出羽である」として、「北陸道は奥羽からの帰郷するための帰り道」に過ぎないとし、『おくのほそ道』の本文の「ことし元禄二とせにや、奥羽長途の行脚只かりそめに思ひたちて」の「奥羽長途の行脚」こそ、今回の芭蕉の目的であったとするのである。
これらの芭蕉の奥の細道行脚の目的の考察の後で、その酒田・象潟の章の検討に入り、ここで、誰もが気がついていたけれども、それほど強調しなかった、次のような記述を、井本氏は記しているのである。
「『おくのほそ道』の象潟の描写は、太平洋岸の松島の文章を意識しているような、調子を高めた文であって、そのことはすでに緒家の説くところである。その末尾は『松しまはわらふがごとく、象潟はうらむがごとし。さびしさにかなしびをくはへて、地勢魂をなやますに似たり」と名文の定評がある。そうして文のあとに、芭蕉の発句を二句並べ、さらに曽良・低耳・曽良と合せて五句の発句が並んでいる。『おくのほそ道』のなかで発句が五句も列挙されるのはここだけである。」 〔註:この小論の発端は、ここの井本氏の指摘にあり、平成八年十一月二十六日付けの『読売新聞』の一面のトップ記事となった『芭蕉直筆 奥の細道』発見の、「芭蕉自身の筆による七十数箇所に及ぶ貼り紙訂正の跡をとどめた草稿本」の、この「貼り紙訂正」の、最も顕著な部分であり、このことについては、後に詳述することとする。〕
続けて、井本氏は芭蕉の『野ざらし紀行』・『鹿島詣』・『更科紀行(乙州本)』に触れ、次の通りの自説を展開するのである。
「奥羽の歌枕・名所・旧跡・古い習俗・古伝説等々に接する願いはかなえられた。またもう一つの旅の目的であった、自分の文学の停滞に対する、新たな開拓の見通しもついた。それは羽黒山下の呂丸に対してはじめて語った不易流行の哲学である。
旅の二つの目的はかなえられ、したがって旅は終った。山頂をきわめたところで登山は終る。芭蕉の旅は終ったのである。旅の終ったところで紀行も終るのが当然であるから、芭蕉は象潟の章を書いて『おくのほそ道』を一旦擱筆(かくひつ)した。
『おくのほそ道』の最後に、他の紀行のように発句が列挙されないのは、象潟までで紀行がいったん完結されていたからであろう。他の理由もないとはいえないが、それが有力な理由であろう。
酒田を立って以後の北陸道の旅は、目的の終った旅のあとの帰り路であり、いわば山頂をきわめた登山のあとの下山である。それは付録である。旅が付録であるとすれば、その旅の記録も付録たらざるをえない。酒田出立以後の『おくのほそ道』は正編に対して続編であり、少し強くいえば付録である。だが、続編であり、付録だからといって価値が低いというのではない。」
長い引用となったが、ここが、井本氏のこの『おくのほそ道』二部構成論の山場なのであろう。そして、この山場の後、氏は続けて二節ほどその論理の展開をしている。
その一つは、『おくのほそ道』の一応の完結の後での、後半の旅の記録をどうするかについての、芭蕉の考え方にふれ、そして、その後で、正編の序文の「月日は百代の過客にして--」に比して、「酒田の余波日を重て、北陸道の雲に望。--、〈荒海や佐渡によこたふ天河〉」は、続編の序文に当たるというのである。
井本氏は、この『芭蕉とその方法』の、その「あとがき」で、「本書に収録した『おくのほそ道二部構成論は私がかねてから抱いていたもので、芭蕉の『おくのほそ道』は奥州の旅を書いたところで一応完結するはずであり、芭蕉は当初そのつもりで書き進め、出羽の歌枕であり名所でもある象潟で一旦筆を収めたとするものである。この構想だけは世に問うてみたいと思っていた。書名を『芭蕉とその方法』としたのは、芭蕉の紀行執筆の方法を始めとして、芭蕉の方法に関するものが少なくないからである。それは私の多年の芭蕉研究を通しての関心事であった」(氏の直接の「あとがき」を編集人が一部要約しているものを用いている)と述べているように、井本氏ならではの、「この構想だけは世に問うてみたいと思っていた」に相応しい、実に、唐木順三氏のそれと同様に、画期的な、『おくのほそ道』の二部構想論といえるものであろう。
(三)
さて、この井本農一氏の「おくのほそ道二部構成論」は、この小論の本題ではなく、前の(二)の註で触れた通り、どちらかというと、この小論の本題は、平成八年十一月二十六日付けの『読売新聞』の一面のトップ記事を飾った『芭蕉直筆 奥の細道』にある。そして、その『芭蕉直筆 奥の細道』と井本農一氏の「おくのほそ道二部構成論」との比較検討、そして、できうることならば、新しい「奥の細道にかかわる構想論」が展開される余地はないのだろうかという、大変に興味深々たるテーマを抱いているというのが、この小論の底流に流れている意図なのでもある。 ここで、今世紀最大の発見とされる『芭蕉直筆 奥の細道』の内容等について触れることとする。
この『芭蕉直筆 奥の細道』(岩波書店)が刊行されたのは平成九年一月二十四日、そして、書店で市販されたのは、その一月二十九日(読売新聞広告)のことである。この書の帯文は、「今世紀最大の発見!二百五十年ぶりに姿を現した幻の自筆本.芭蕉研究に新たな問題を提示する一級資料.創作方法の秘密を解明するおびただしい推敲の跡.現在緒本のもとになる芭蕉の自筆草稿本いわゆる「野坡本」の出現.全編数十カ所におよぶ貼り紙訂正箇所の解読は、彫琢の名文家の文章のあとをたどり、その創作方法の秘密を解明する糸口ともなる.最新鋭の高精細な製版技術で原寸復刻された影印とその忠実な翻字,また句読点などを付して読みやすく活字におこした本文,貼り紙の下に隠された文字を読み取って注記,懇切な解説などで構成.」とある。まさに、この『芭蕉直筆 奥の細道』に触れての第一印象は、この岩波書店の編集人の記述による帯文の一つ一つが、しっかりと胸に突き刺さるような思いなのである。
ここで、その帯文の「懇切な解説」の一つでもあり、この「幻の自筆本」の鑑定にも大きく貢献した上野洋三氏の「芭蕉の書き癖」(『前掲書』所収)から、『奥の細道』の緒本の系統図を見ていくこととする。
④自筆本(芭蕉筆)・・・③曽良本(利牛筆) ・・・・
③曽良本書込(芭蕉筆)・・・②柿衞本(素龍筆)
・・・①西村本(素龍筆)
(説明)『奥の細道』の緒本
① 西村本(素龍筆):西村弘明氏所蔵、昭和二十三年、潁原退蔵解説付きの複製本が刊行され、この書が今日の『奥の細道』の 大部分の底本となっている。
② 柿衞本(素龍筆):柿衞文庫所蔵、昭和三十五年、岡田利兵衛の紹介と翻刻がなされている。
③ 曽良本(利牛筆)・曽良本書込(芭蕉筆) :天理図書館所蔵、昭和二十年代半ばに杉 浦正一郎氏の蔵となり、この書と『曽良随 行日記』(昭和十八年に山本六丁子氏が翻 刻)関連する杉浦博士の一連の研究が『芭 蕉研究』(岩波書店)に収められている。 昭和四十七年に宮本三郎解説付きの複製が 『芭蕉紀行文集』に収録されている。この 曽良本を利牛筆とし、その書き込みを芭蕉 筆としたのは今回の上野洋三氏であって、 芭蕉自筆本の発見と併せて、大きな発見の 一つとも理解できる。
④ 自筆本(芭蕉筆):中尾堅一郎氏蔵、桜井武次郎・上野洋三氏の鑑定の結果、真蹟とされ、いわゆる幻の書とされていた芭蕉 自筆本(野坡本)として、中尾松泉堂創立八十周年記念出版として複製本が作られ、そして、この平成九年一月の岩波書店での刊行とつながったのである。
*書型:枡形本(一四・八センチ ×一六・八五センチ 、但し、改装による化粧裁ち)
*内題:「おくの細道」(註・西村本の芭蕉筆とされている題名『おくのほそ道』とは相違して いる)
*紙数:三十四丁(本文三十二丁)
*本文行数:十一乃至十六行(半丁)
*所蔵の経路:芭蕉--野坡--梅従--有国(寛政版『おくのほそ道』など蔵板者階山堂・浦 井徳右衛門隆屋)〈桜井武次郎「芭蕉自筆『奥の細道』について」(『前掲書』所収)〉
〔註〕:以下、①については『西村本』・②については『柿衞本』・③については、『曽良本』(上野洋三氏は『天理本』という所蔵者の名の名称で呼ぶことの検討などを提案している)・④については『自筆本』という名称を用いることとする。
さて、今回の『自筆本』においては、尾形仂氏の「序」にもある通り、「芭蕉自身の手による七十数か所に及ぶ貼り紙訂正の跡をとどめた」という、その尾形氏の言葉を借りれば、「胸のときめき」覚える、それこそ、この本の岩波書店の編集人による帯文の「今世紀最大の発見!」という感じが一番的を得た表現のようにも思われるのである。
そして、その最も大きな「貼り紙訂正の跡をとどめた」箇所の一つに、この『自筆本』の「本文篇」の四十六(象潟逍遙)の箇所があげられるのである。その『自筆本』の九十九頁の脚注の訂正前(貼り紙の下に記載されているものをコンピュータ・グラフイックなどによって解読したもの)と、その訂正後(貼り紙訂正のもの)とを比較してみると、次の通りとなる。
① 訂正前
「 を□□□□の祭り也幾代になりぬ象潟の神と□□代の神の祭にやとゝへは 曽良 象潟の料理何食ふ神祭 」
① 訂正後
「 祭礼 曽良 象潟の料理何くふ神祭 」
② 訂正前
「 みのゝ国の商人酒田より跡をしたひ来りて
蜑の家に戸板敷てや夕涼 」
② 訂正後
「 美濃国商人 低耳 蜑の家や戸板を敷て夕すゞみ 」
③ 訂正前
「 荒磯の岩の上にみさこの巣有
寛々たる雎鳩のちきりおもひ寄てたるにや 曽良 ミサコ
波こえぬ契ありてや雎鳩の巣 」
③ 訂正後
岩上に雎鳩の巣を見る 曽良
波こえぬ契ありてやみさごの巣 」
これらの他に、比較的大きな訂正箇所は、『自筆本』の「本文篇」の十三(遊行柳)・十六(須賀川駅)・二十七(故人の心)・三十(勇義忠孝)・三十一(松島逍遙)・四十(富める者)・四十二(芦角一声)などである。これらに比しても、前に掲げた、四十六(象潟逍遙)は、二丁(頁)に跨がっての貼り紙三枚による『自筆本』最大の大幅の訂正箇所といっても差し支えなかろう。
この『自筆本』最大の大幅の訂正は、何を意味するものなのであろうか。井本農一氏の言葉を借りていえば、「芭蕉の紀行執筆の方法」(『前掲書』)として、これらの大幅の訂正は、何を意味するものなのであろうか。 この答えこそ、井本農一氏の「この構想だけは世に問うてみたいと思っていた」、その、「おくのほそ道二部構成論」の「芭蕉の発句を二句並べ、さらに曽良・低耳・曽良と合せて五句の発句が並んでいる。『おくのほそ道』のなかで発句が五句も列挙されるのはここだけである」(『前掲書』)という指摘と、まさに寸分の違いもなく符合するのである。 すなわち、『自筆本』最大の大幅の訂正の「象潟逍遙」の芭蕉の記述は、まさに、芭蕉の最高紀行文であり、尾形仂氏の言葉を借りてすれば(『前掲書』)、「世界の古典」である『おくのほそ道』の構成が、「酒田出立以後の『おくのほそ道』は正編に対して続編であり、少し強くいえば付録である」とする井本農一氏の世に問うている「おくのほそ道二部構成論」の、何よりの証明になるのではなかろうか。いや、これらの『自筆本』最大の大幅の訂正の「象潟逍遙」の芭蕉の記述以外にも、井本氏のいう「正編」と「続編」との二部構想論では、芭蕉以外の曽良等の発句とその作者との記述方法が、全然相違しているのである。このことは、『自筆本』の「影印翻字篇」を見て改めて思い至ったものである。それらの箇所を次に例示をしてみたい。
○ 井本農一氏の『おくのほそ道』(正編)
三オ(三丁表)
① 剃捨て黒髪山に衣替 曽良
四ウ(四丁裏)
曽良
② かさねとは八重撫子の名成へし
六ウ(六丁裏)
キ 曽良
③ 卯の花をかさしに関の晴着哉
十四オ(十四丁表)
曽良
④ 松島や鶴に身をかれほとゝぎす
十六オ(十六丁表)
⑤ 卯花に兼房みゆる白髪哉 曽良
十七ウ(十七丁裏)
⑥ 子飼する人は古代の姿哉 曽良
二十一オ(二十一丁表)
曽良
⑦ 湯殿山銭ふむ道のなみた哉
二十二ウ(二十二丁裏)
祭礼 曽良
⑧ 象潟や料理何くふ神祭
美濃国商人 低耳
⑨ 蜑の家や戸板を敷て夕すゝみ
岩上に雎鳩の巣を見る
曽良
⑩ 波こえぬ契ありてやみさごの巣
これらの、井本農一氏のいう「正編」に対して、氏のいう「続編」の後半の部分の、曽良の句の、その曽良の名は、その「正編」において例示してきたように、句の下に、独立して記述されないで、実に、本文の中に、曽良という名が記載されているという、大きな相違点を見いだすことができるのである。次に、その「続編」の後半の部分の曽良の句の記述箇所を例示することとする。
○ 井本農一氏の『おくのほそ道』(続編)
二十六ウ(二十六丁裏)
曽良は腹を病みて伊勢の国長嶋
と云処にゆかりあれは先立て旅
立行に
⑪ ゆきゆき(註)てたふれ伏共萩の原
(註):『自筆本』は二倍送りの記号
二十六ウ(二十六丁裏)~二十六オ(二十七丁表)
大聖持の城外全昌寺と云寺に
泊る猶かゝの地也曽良も前の夜此寺に泊りて
⑫ 終夜秋風聞やうらの山
さらに、井本農一氏の「おくのほそ道二部構成論」を証明するものとして、井本氏がいう「酒田出立以後の『おくのほそ道』は正編に対して続編であり、少し強くいえば付録である」という、そして、さらに氏がいう「芭蕉は正編を書くときは畏まっていたのだが、続編にいたってややリラックスしている気がする」(『前掲書』)という、そのことに関連して、『自筆本』の「影印翻字篇」においては、実に大幅の訂正箇所は少なく、単に誤字・脱字を訂正するような箇所が多いということも確実に指摘できるように思われる。わずかに、大幅な訂正箇所は、二十五オ(二十五丁表)の「一笑追善」に関する訂正があげられるであろう。
以上、今回発見された、芭蕉の『おくのほそ道』の『自筆本』において、その「影印翻字編」を詳細に検討していくと、まず、その二十二ウ(二十二丁裏)から二十三オ(二十三丁表)にかけての「象潟逍遙」の箇所の、貼り紙による大幅訂正、そして、芭蕉の句以外の曽良と低耳の十二句について、「象潟逍遙」の以前とその後では、その作者の名の記述方法が典型的に相違しているということ、さらには、その「象潟逍遙」の以前とその後では、その後の方が、極端に、貼り紙による大幅訂正が少ないという事実からして、平成二年六月の「橘」に発表した「『おくのほそ道』二部構成論序説」と、その年の十二月の「俳文芸」に公表した「『おくのほそ道』二部構成論」(いずれも平成五年刊行の『芭蕉とその方法』所収)は、誠に的確な、且つ、十分に説得力のある説であることを確信するものなのである。
しかし、ここまできて、一つ重大なことに気がついたのである。すなわち、その重大なことと思われることは、今回発見された、芭蕉の『直筆本』においては、芭蕉の発句数は五十一句であり、『西村本』・『柿衛本』・『曽良本』(この本では五十一句が記載されているが、そのうちの一句が見せ消ちされている)の五十句と比して、一句多いということなのである。この一句多いということは何を物語るのであろうか。その一句とそれに並列されている句とを、次に記述することとする。そして、現在の『おくのほそ道』では見ることのできない、その幻の一句に●印を付し、それと並列しての『自筆本』における、その前句に○印を付し、そして、『西村本』などでの推敲を経て最終作品となったその句に☆印を付することとする。
○ 五月雨や年どし(註)降も五百たび
(註):『自筆本』では「どし」は濁点のある二倍送り記号
☆ 五月雨の降残してや光堂
● 蛍火の昼は消つゝ柱かな
(四)
さて、「今世紀最大の発見!二百五十年ぶりに姿を現した幻の自筆本」とされる今回の芭蕉の『自筆本』は、井本農一氏が、「この構想だけは世に問うてみたいと思っていた」 という「おくのほそ道二部構想論」を充分に裏付けるものであるということについては、いささかの疑念を挟む必要はないことを痛感するものである。
しかし、井本氏がその『芭蕉とその方法』の「あとがき」で、「書名を『芭蕉とその方法』としたのは、--、芭蕉の紀行執筆の方法を始めとして、論考のなかに芭蕉の方法に関するものが少なくないからである。それは私の芭蕉研究を通しての仕事であった」という通り、例えば、その「『笈の小文』と『おくのほそ道』との関係」(初出:「成蹊国文(昭和四十三年)」)などによると、芭蕉の不朽の力作の『おくのほそ道』が、単純な、「おくのほそ道二部構想論」のみではなく、無数の緒家による「おくのほそ道構想論」が先に引用した井本氏の言葉でいうならば「それぞれ一里にあって捨てがたい」というほどに、その他、沢山の伏線が隠されていることも事実であろう。
とすれば、井本氏自身も、その「おくのほそ道二部構想論」だけで、芭蕉の『おくのほそ道』の全体を包含したプロット(構想・骨組み)とは、よもや考えていないではなかろうか。すなわち、井本氏の「おくのほそ道二部構想論」は、芭蕉の立てた一番外側の枠の大きいプロットであって、その大枠の下で、多分に、芭蕉は、綾取りのような工夫に工夫を凝らした中・小のさまざまなプロットを、この自分の最後の紀行文の、そのさまざまの所に、その推敲の限りをつくしているに違いないのである。
そして、「自分の(最後の紀行文の『おくのほそ道』を完成するための)、自分による(推敲に推敲を重ねての自分の手による)、自分のための(新しい『不易流行』を産むための)」の、この「世界に冠たる」文芸作品の『おくのほそ道』の構成は、「序章」(『自筆本』の『本文篇』の『一 漂泊』)」と、「正編」(『自筆本』の『二 離別』から『四十六 象潟逍遙)』)と、そして、「続編」(『四十七 北陸道』から『六十二 蘇生』)との三部構成論が成り立つということも、やはり、井本農一氏の二部構成論との延長線上での、「芭蕉とその方法」の一つとして考えられるのではなかろうか。すなわち、その三部構成論の試論の、その出だし句と結びの句及びその収録句数は次の通りとなる。
○第一部(序章)--草の戸も住替る代そ雛の家
*第一部の収録句:一句(脇句以下の七句は省略)
○第二部(正編)--行春や鳥啼魚の目は泪
--波こえぬ契ありてやみさごの巣(曽良)
○第三部(続編)--文月や六日も常の夜には似ず
--蛤のふたみに別行秋そ
*第一部・第二部の収録句:芭蕉の句・五十句
曽良の句・十一句
低耳の句・ 一句
(註)これは今回発見された『直筆本』での芭蕉の奥の細道構想の発端になるものであって、成稿となった『西村本』などでの第一部・第二部の収録されている芭蕉の句数は四十九句となり、その一句の相違は、永遠に芭蕉の『おくのほそ道』は、未完成であることを暗示しているのかも知れない。
なお、中田亮氏は「『おくのほそ道』の構想論」(「文星紀要第七号」)で、百韻形式の「五段落構成論」(一・出立まで 二・平泉以前 三・平泉以後 四・象潟以後 五・ひとり行脚)をとっており、そして、この五・ひとり行脚(大聖寺から大垣まで)を百韻形式の「名残の表」にあたるとし、その収録句数を七句として、敢えて、「名残の表」の八句を七句として「揚句」を省略したのは「この作品(『おくのほそ道』)が永遠に未完成であるということを意図しての結果」との推測をほどこしている。これらの点については、今後の課題として特に付記をしておきたい。
下野における芭蕉の俳諧
下野における芭蕉の俳諧
元禄二年( 一六八九) 三月二十七日、松尾芭蕉は江戸深川を出発した。門人河合曽良を伴って、旅程六〇〇里五ヶ月余りにわたる『おくのほそ道』の紀行の始まりである。
千住から北へ向かって真っ直ぐに、春日部・間々田・鹿沼・日光・玉入( 玉生) を経て、那須の黒羽の鹿子畑翠桃( すいとう) を訪ねたのは、四月三日のことであった。芭蕉はここで翠桃や兄の桃雪( とうせつ) の歓待を受け、江戸出発以来の疲れを癒すこととなる。桃雪は、本名を浄法寺図書高勝といい、黒羽の領主大関氏の留守居役を務める人であった。
この逗留の間、翠桃や桃雪などを連衆に俳諧が興行された。これが、『おくのほそ道』紀行中における俳諧第一作であり、『曽良旅日記』に記録されている。また、この歌仙は、芭蕉の三回忌を期して自ら奥羽行脚を決行した天野桃隣によって、元禄十年( 一六九七) に編集された『陸奥鵆( むつちどり) 』に、かなりの改作( 芭蕉の推敲を経たものとも思われている) を経て収録されている。
この歌仙は、主客として芭蕉がまず発句を詠み、亭主の翠桃がそれに脇句を付け、相伴の曽良が第三を付けて興行された。その連句作品数は、芭蕉・八、曽良・八、翠桃・八で、その他の連衆として翅輪・五( 『陸奥鵆』
では六) 、桃里・四、二寸・一、秋鴉( 桃雪) ・一となっている。この翅輪、桃里、二寸については、津久江翅輪( 『曽良日記』では津久井とある) 、蓮見桃里( 余瀬の本陣問屋) 、森田二寸との考証がなされている。
さて、この歌仙については、柳田国男著『俳諧評釈』において、さらには、東明雅著『芭蕉の恋句』等でも取り上げられており、ここでは、この歌仙鑑賞というよりは、この歌仙を通して、俳諧( 歌仙・連句) とは何か、歌仙の構成や式目( ルール) また発句( 俳句) と俳諧の関係等ということに、その主眼点を置き、その総論的な考察を進めることにしたい。
歌仙「* 秣( まぐさ) おふの巻」* = 秣は草冠
歌仙とは、三十六句形式の連句のことである。連句とは、何人かの人が寄り集まり( 連衆ともいう) 、一定のルール( 式目ともいう) のもとに、五七五の詩句( 長句ともいう) と七七の詩句( 短句ともいう) とを交互に連ねて一巻の作品を完成させるところの、協同制作の詩編のことをいう。なお、題目が定まっているものではないが、ここでは、その発句を、便宜上、掲げておくことにする。
連句を記載するには、通常、縦・約四〇センチ、横・約六〇センチの料紙( 懐紙ともいう) が用いられる。その懐紙を二つ折りにして、歌仙の場合には、二枚用いられる。その一枚目を、初折( その表はオ、裏はウ) 、二枚目を名残の折( その表はナオ、裏はナウ) という。
奈須余瀬翠桃を尋( たづね) て
この歌仙の前書きである。奈須は那須、余瀬は、今の、栃木県那須郡黒羽町に属する地名である。「翠桃を尋( たづね) て」は、発句の動機を示したものである。
秣( まぐさ) おふ人を枝折( しをり) の夏野哉芭蕉
発句、「夏野」で夏。発句とは、連句の巻頭の句をいう。発句は、必ず、季語と切字を含んでいなければならない。逆に、五七五の十七音形式と季語・切字の条件を備えていれば、たとえ、それが、単独で詠まれたものであっても、発句と呼ばれるようになり、後には、連句の巻頭として詠まれるものを、立句( たてく) 、単独で詠まれるものを、地発句( じほっく) と称する区別も生じた。正岡子規によって命名された、今日の俳句は、この地発句に当たるものである。
「発句の事は一座巻の頭なれば、初心の遠慮すべし。『八雲御抄( やくもみしょう) 』にも其( その) 沙汰有( あり) 。句姿も高く、位よろしきをすべしと、昔より云( いひ) 侍る。先師( 私注・芭蕉)は懐紙のほ句( 私注・発句) かろきを好( このまれ) し也。」( 服部土芳著・『三冊子』)
〔句意〕広大な那須野の中の、あなたのお宅を尋ねる時、秣を背負ったひとが、道しるべになってくれまして、大層助かりました。
( 秣( まぐさ) おふ人を枝折( しをり) の夏野哉)
青き覆盆子( いちご) 〈を〉こぼす椎の葉翠桃
脇句、「覆盆子」で夏。〈を〉は、『陸奥鵆』による補訂。脇句は、発句と調子・用語などを相通ずるようにしなければならない。脇句は、韻字止め( 体言で止めること) にした方が良いとされる。さらに、脇句は、発句と同じ季を持たせる必要があるとされている。連句における季の約束については、春夏秋冬の季を含む句と、雑( ぞう) の句( 無季の句) とが、ほどよく配分され、全巻として、変化と調和が巧みにとられている必要があるとされている。このようなことから、歌仙の場合、「同季五句去り」( 同じ季を含んだ句は少なくとも五句隔てて付ける) 、景物( 詩の題材) の多い春・秋の句が出た場合は、三句まで続け、夏・冬は一句ないし二句で捨てるというようなルールが存在する。
「脇は亭主のなす事、昔より云( いふ) 。しかれども首尾にもよるべし。客ほ句( 私注・発句) とて、むかしは必( かならず) 客より挨拶第一にほ句( 発句) をなす。脇も答( こたふ) るごとくにうけて、挨拶を付( つけ)侍る也。」( 『三冊子』)
〔句意〕折角お出で下さったのに、何のおもてなしもできず、せめてお盆に代わり、風流にと椎の葉に苺を盛って差し上げましたら、苺がその椎の葉からこぼれてしまいました。
( 青き覆盆子( いちご) 〈を〉こぼす椎の葉)
村雨に市のかりやを吹( ふき) とりて曽良
第三、雑の句( 心は、前二句の夏の季に思いを馳せている) 。発句は、漢詩でいえば、起句にあたり、脇句は承句、第三は転句に当たる。すなわち、第三は、俳諧一巻における変化の始まりである。発句と同じような句姿・句意であってはならず、思い切って離れなければならない。そして、その留めは、「に留、て留め、にて留め、らん留め、もなし留め」などが普通である。
「第三の句、第一の難儀の場所也。上手の入ると云( いふ) は第三也。発句の打越( うちこし) 、脇の句にはなれて付( つくる) を上手の手際とは云也。しかも第三のふりを持て、留りに去嫌ひあれば、第一の難所也。一巻の出来・不出来、脇・第三より極( きはま) る也。」( 森川許六・他編・『宇陀法師』)
〔句意〕( その青い苺を売っている) 物売り市の小屋掛けが、村雨まじりの突風で吹き飛ばされてしまいました。
( 村雨に市のかりやを吹とりて)
町中を行( ゆく) 川音の月はせを( 私注・芭蕉)
オ・四句目、「月」で秋。五句目が月の定座( じょうざ) であるが、この四句目に、その定座が引き上げられいる。ちなみに、定座より後に来ることを、定座をこぼすという。芭蕉は、前句が村雨という天象の句なので、五句目の月の定座で月を詠むと、一巻の進行が前に進まず、後戻りすることになり、この輪廻( りんね) を嫌い、ここに、同じ天象の月の句を詠み、定座を引き上げたという。
「四句めは、むかしより四句目ぶりなど云て、やすくかるきをよしとす。師( 私注・芭蕉) のいはく『重きは四句目の体にあらず、脇にひとし。句中に作をせず』と也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( 村雨混じりの突風で市の小屋掛けが吹き飛ばされた夕暮れ、) 何時しかすっかり晴れ渡り、空には月がかかりました。そして、その街の中を一条の川音が聞こえてきます。
( 町中を行( ゆく) 川音の月)
箸鷹( はしたか) を手に居( すゑ) ながら夕涼翠桃
オ・五句目、「箸鷹」で秋。箸鷹は「はいたか」ともいう。「夕涼」は夏の季語でもあるので、『陸奥鵆』では、「鷹の子も手に居ながらきりぎりす」と改作されている。秋の句( 前句・月) が出ると、最低三句は続けるというルールがあり、この句は秋の句。
「五句め、七句めの事『三て五覧』( 私注・第三は「て」留まり、五句目を「らん」留めにするのが良い) などゝ古説あり。七句めも同じ心得也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( 空には月がかかり、街の中を一条の川音が聞こえますが、) その川べりを、鷹を手にして、鷹を飼い馴らしている老人が、夕涼みをしています。
( 箸鷹( はしたか) を手に居( すゑ)ながら夕涼)
秋草ゑがく帷子( かたびら) はた〈私注・誰〉そソラ( 私注・曽良)
オ・六句目( 折端ともいう) 、「秋草」で秋。帷子は、夏の季語でもあるので、『陸奥鵆』では、「萩の墨絵の縮緬は誰」と改作されている。この句は、秋草に象徴されるような佳人が登場してきたことにより、次の句に、恋の句を誘い出そうとするような句で、恋の呼び出しの句といわれる。
「その一句だけでは恋の句とは考えられないが、何となく恋の余情、余韻を示唆するところがある句を『恋の呼び出し』という。」( 東明雅・他編『連句辞典』)
〔句意〕( その鷹を手に据えた老人の側には、) 秋草模様の華やかなな絵帷子を着た美しい人がひとり、あの人は誰なのでしょう。
( 秋草ゑがく帷子( かたびら) はた〈私注・誰〉そ)
ものいへば扇子に* ( かほ) をかくされてはせを*=異体字
ウ・初句( 折立〈おったて〉ともいう) 、恋の句で、雑の句。扇子は、夏の季語でもあるので、『陸奥鵆』では、「物いへば小傘に顔を押入るゝ」と改作されている。
「六句目までを表六句といって、序・破・急の序にあたる部分とし、神祇・釈教・恋・無常、その外述懐・懐旧・病体・軍体・地名・人名など、あまりけざやかなものをここに持ち出すことを忌まれているのに対して、この七句目からは破の段に入るから、先にのべたようなものがすべて解禁になる。俳句( 連句) 一巻は、この辺り
から次第に盛り上がって来るのである。だが、ここが肝腎なのであるが、すべての禁忌が解除されたからと言って、すぐさま神祇・釈教・恋・無常、その他を持ち出すのは、あまりにはしたないと言うか、現金だと言うか、そのように昔の人は考えていたようである。だから、禁忌が解除になった途端に、第七句目に恋の句を出すのを『待兼の恋』と言って、嫌ったこともあったようである。芭蕉も『待兼の恋』ということがあって、それを嫌う人たちのあること、そしてその理由も知っていた。知り抜いていたであろう。しかし、彼はそのことにこだわっていない。第六句目に曽良の『恋の呼び出し』があると、それに素直に応じてはっきりと恋の句を付けた。このようなところに、いかにもとらわれない柔軟な芭蕉の精神を見ることができる。」( 東明雅著『芭蕉の恋句』)
〔句意〕( 秋草模様の華やかなな絵帷子を着た美しい人に、) 言葉をかけましたら、恥ずかしげに、扇子で顔を隠されてしまいました。
( ものいへば扇子に* ( かほ) をかくされて) * = 異体字
寝みだす髪のつらき乗合翅輪
ウ・二句目、恋の句で、雑の句。ここで、翅輪が登場する。表六句は、芭蕉、翠桃、曽良の三吟で二順しているが、この初裏の十二句で、翅輪が加わり四吟で進行する。「乗合」は、「乗合舟」の略で、この八句目で、乗合舟の中に場面が転ぜられている。「寝みだす髪」は、閨の中を連想するとされ、『陸奥鵆』では、「みだれた髪のつらき乗合」となっている。
「恋の句は人情の句の最たるもので、一巻の中に恋の句が詠まれていないと、その巻は不完全なものであるといわれる程で、連句では月・花と同じく大事なものとされている。( 中略) 芭蕉は恋の句は一句で捨ててもよいとはしているが、実際は恋の句が二句以上続くことが多い。」( 『連句辞典』)
〔句意〕( 扇子で顔を隠されましたその人は、) 乗合舟の中で、しきりに乱れた髪を気にしておられます。
( 寝みだす髪のつらき乗合)
尋( たづぬ) ルに火を焼付( たきつく) る家もなし曽良
ウ・三句目、雑の句。前句を早朝と見て、「火を焼付( たきつく) る」と、朝の炊事の場面に転じている。
「先師( 私注・芭蕉) 曰、ほ句( 私注・発句) はむかしよりさまざま替り侍れど、付句は三変也。むかしは付物を専らとす。中比( 私注・頃) は心付を専とす。今は、うつり( 私注・移り) 、ひゞき( 私注・響) 、にほひ( 私注・匂) 、くらゐ( 私注・位) を以て付るをよしとす。」( 向井去来著『去来抄』)
〔句意〕( その乗合舟は、) 朝の暗い中を岸辺に着きましたが、朝餉の支度なのに火を焚きつけている家とてなく、ものを尋ねるにも、どうしたら良いか、本当に途方にくれました。
( 尋( たづぬ) ルに火を焼付( たきつく) る家もなし)
盗人こはき廿六( とどろく) の里翠桃
ウ・四句目、雑の句。「廿六( 二十六) 」の読みは、中田亮著『下野俳諧史』による。なお、柳田国男著『俳諧評釈』では、「とどろき」、中村俊定・他校注の『芭蕉連句集』では「はたむり」とある。今市から鬼怒川沿いに、「轟」という地名があるが、とにかく、辺鄙な里の名であろう。
「国名: 国の名や地名を詠み込むことで、初折の表には出さないことになっている。二句去りで一句から二句続けるが、現代連句では片仮名の外国名も多く見られる。」( 『連句辞典』)
〔句意〕( 朝飼の支度に火も焚きつける家もない) この川辺の里は、恐ろしい盗人が出るということで、近辺に轟いています。
( 盗人こはき廿六( とどろく) の里)
松の根に笈をならべて年とらんはせを
ウ・五句目、「年とらん」で冬。「笈」は、行脚僧が仏具・衣類などを入れて背に負う脚・開き戸のついた箱のこと。
「付( つく) といふ筋は、匂・響・俤・移り・推量などゝ、形なきより起る所也。こゝろ通ぜざれば及がたき所也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その恐ろしい川辺で、) 大晦日の夜、二人の行脚僧が、松の根に笈を置きながら、そして、野火を焚きながら、年越しをしています。
( 松の根に笈をならべて年とらん)
雪かきわけて連哥( れんが) 始( はじむ) る翠桃
ウ・六句目、「雪」で冬。『陸奥鵆』では、「雪になるから」で収録されている。
「付味: 付句を前句のどこに着目して付けた『付所』とか、どのような案じ方で付けた『付心』とか、どのような意味内容の句である『句意』とかを吟味するのではなく、前句の句意以外の雰囲気的な勢いや情調といった言外余情的な要素が、付句にどのように感合し合い映発し合って、どのような余情を醸し出しているかを吟味するものである。」( 『連句辞典』)
〔句意〕( 松の根で野宿して年越しをしている二人の行脚僧が、) 折りからの雪をかきわけながら、今、静かに、連歌に興じています。
( 雪かきわけて連哥( れんが) 始( はじむ) る)
名どころのお〈私注・を〉かしき小野ゝ炭俵( ママ) ( 私注・翅輪)
ウ・七句目、「炭」で冬。『俳諧書留』で、曽良は、この付句の作者を書き落としている。『陸奥鵆』では、翅輪と記してあり、句順からしても、それが正しいとされている。「名どころ」は名所。「おかしき」は風雅で情趣のあるさま。「小野ゝ炭俵」は炭の産地の小野の炭俵の意。また、初裏の月の定座は、後世になって、この七句目とされるようになったが、この頃は、おおよその月を出すべき位置として弾力的に運用されていたという( 尾形仂著『歌仙の世界』) 。
「この付句は、前句が、『わすれてはゆめかとぞ思ふおもひきやゆきふみわけて君をみんとは』( 『古今和歌集』の在原業平の歌) の本歌取りで、その業平の歌の前書きに由来がある」( 阿部正美著『芭蕉連句抄』) という説もある。
「本歌取といふは、古歌の詞を取合て付るを云ふ。」( 『三冊子』)
〔句意〕( 雪の中で連歌に興じている二人の僧を見ていますと、) あの業平が詠んだ雪中の連歌の歌が偲ばれてきます。そして、その歌の前書きの中の、名にしおう炭の産地の小野の炭俵のように、俵は粗雑であってもその炭は殊の外味わいがあるように、その二人の行脚僧の光景は、みすぼらしい姿はしていますが、真に風雅で趣のある様でした。
( 名どころのお〈私注・を〉かしき小野ゝ炭俵)
碪( きぬた) うたるゝ尼達の家曽良
ウ・八句目、「碪」で秋。この句は、「色変る小野の浅茅の初霜に一夜もかれずうつころもかな」( 『新千載集』) に由来があるとされている。
「『碪』は秋の季語で、詩や和歌にも多く詠まれているが、李白の『子夜呉歌』に『長安一片月万戸擣衣声秋風吹不尽総是玉関情何日平胡虜良人罷遠征』とうたわれているように、必ず月と結びつき、また女子が夫を思う情と結びついている。だから、『碪』という語が出ただけで、次句に恋句をさそう『恋の呼び出し』になる。」( 『芭蕉の恋句』)
〔句意〕( その小野の里では、) 身分の高い尼達のおられます家から、砧を打つ音が聞こえてきます。
( 碪( きぬた) うたるゝ尼達の家)
あの月も恋ゆへ〈私注・ゑ〉にこそ悲しけれ翠桃
ウ・九句目、「月」で秋。恋の句。ここでは、初裏の月を定座より一句こぼして出している。
「この尼さんたちは、もう恋にも愛にも関係のない身になり果てている。しかし木石の身でない以上、そのような悟りきった境地に達するのはなかなか大変であろうし、また髪は剃っても本当に忘れることのできない思いもあるだろう。そのように、過去にいろいろの思い出のある尼たちが、一緒に碪をうちながら、昔を語り合っているのである。」( 『芭蕉の恋句』)
〔句意〕( その尼達の語らいの中に、) 「あの、今日の、あの月のような夜に、悲しい悲しい恋の思い出がございます」との、しみじみとしたやりとりがありました。
( あの月も恋ゆへ〈私注・ゑ〉にこそ悲しけれ)
露とも消( きえ) ね恋のいたきに翁( 私注・芭蕉)
ウ・十句目、「露」で秋。恋の句。「翁」は、芭蕉の敬称、この巻では、ここで初めて用いられている。「ね」は、完了の助動詞「ぬ」の命令形、「露のように消えてしまえ」の激しい気持ちを表したもの。
「この『露とも消ね』の露は前句を付けた場合、すばらしい効果を発揮している。もともと、月と露とは貞門の時代からの付合語であるが、『あの月も』と指すあたりの野辺の露を連想させるとともに、露のようにはかない命をも連想させよう。そして『胸のいたき』には、つれない人を恨む気分がこめられ、それがはっきり言い切られていないところに、綿々とした尽きない情がたゆたっているように思われる。おそらく前句は、恋に破れた若い女性が泪を一ばい浮かべながら、月を見入っているところであろうが、芭蕉はその句を受けて、その女性になりかわって、その心の痛みを述べている。芭蕉は本当にその女性になった気でこの句を作ったのだろう。そして美しくここに謳われている。」( 『芭蕉の恋句』)
〔句意〕( あの月を眺めていますと、) 本当に胸が張り裂けるばかりで、この身も、この露のように、はかなく消えてしまえと、そのように、もう、この激しい恋の悶えをどうすることもできません。
( 露とも消( きえ) ね恋のいたきに)
錦秋( きんしゅう) に時めく花の憎かりし曽良
ウ・十一句目、「花」で春、花の定座。「錦秋」は、美しい衣服。「時めく花」は、時を得て栄華を誇っている人を花に例えている。初裏の花の定座で、秋から春への季移りである。
「『花の句』の詠まれるべき所はおよそ定まっているが、四句目は軽い句を出す所であるとされるから、そこには『花の句』は出さない方がよいとされる。また定座から引き上げることはあっても、こぼすことがないのも『花の句』を大事にする表れであろう。」( 『連句辞典』)
〔句意〕( この悶え苦しんでいる私とは対照的に、) あの人は、「今よ、花よ」と栄華を極めているのが、実にうらめしく、切ない気持ちで一杯です。
( 錦秋( きんしゅう) に時めく花の憎かりし)
をのが羽に乗( のる) 蝶の小車( おぐるま) 翠桃
ウ・折端、「蝶」で春。「蝶の小車」は、色々な解があるが、「牛車の形の錦文〈小車錦〉と蝶のこと」と解する。
「蕉門の付句は、前句の情を引来るを嫌ふ。唯、前句は是いかなる場、いかなる人、其業・其位を能( よく)見定め、前句をつきはなしてつくべし。」( 『去来抄』)
〔句意〕( 錦秋のときめく春、) 蝶が、小車錦の蝶の模様の羽に、己の羽を休めています。
( をのが羽に乗( のる) 蝶の小車( おぐるま) )
日がささす子どもを誘( さそひ) て春の庭翅輪
ナオ・折立、「春の庭」で春。定座の花から始まった春の三句目である。これより、名残の裏の始まりである。表は、序・破・急の序、裏は、序の段の序盤から中盤、そして、この名残の裏で、破の段の中盤から終盤という局面である。その初句は、美しい春の景気の句から始まった。
「先師( 私注・芭蕉) 曰、『気色はいかほどつゞけんもよし。天象・地形・人事・草木・虫魚・鳥獣の遊べる、其形容みな気色なる』と也。」( 『去来抄』)
〔句意〕( 錦秋がときめき、蝶が飛び交う春、) 私は、日傘をさし、幼子の手を引きながら、その春の庭にでました。
( 日がささす子どもを誘( さそひ) て春の庭)
ころもを捨( すて) てかろき世の中桃里
ナオ・二句目、雑の句。「ころもを捨て」は、仕官を止めての意味。名残の裏の二句目は、景気の句から人情の句へと転じている。
「『人情の句』は、『自』『他』に大別され、『自』は自分本人の動作・思考・状態等を指すもので、『他』は他人の動作・思考・状態等を指すものである。」( 『連句辞典』)
〔句意〕( その春の庭で胸に去来することは、) それは、仕官を止めて、身も心も、何と軽やかなことかという実感のみである。
( ころもを捨( すて) てかろき世の中)
酒呑( のま) ば谷の朽木も仏也翁
ナオ・三句目、雑の句。名残の裏の最初の芭蕉の付句である。
「名残の裏、随分かろく、やり句勝に、事がましき事をせず、早仕廻べき也。」( 『宇陀法師』)〔句意〕( その官衣を捨てた男は、) 酒に酔い、その酒に酔った目で、谷の朽木を見れば、それは、きっと、仏様の恰好に見えることでしょう。
( 酒呑( のま) ば谷の朽木も仏也)
狩人かへる岨( そま) の枩明( たいまつ) 曽良
ナオ・四句目、雑の句。曽良の、前句の「谷の朽木」から、山の険しい岨道を連想したのであろう。山水画のような景気の句である。
「歌に『景曲は見様躰( みるやうてい) に属す』と定家卿もの給ふ也。」( 『宇陀法師』)
〔句意〕( その谷の朽木のある) 険しい山の岨道を、今、松明をかざして、狩人が家路につくところです。
( 狩人かへる岨( そま) の枩明( たいまつ) )
落武者の明日の道問( とふ) 草枕翠桃
ナオ・五句目、雑の句。「草枕」は、旅の枕詞であるが、単独では、旅とか旅寝( 野宿) などの意。
「連歌に旅の句三句つゞき、二句にてすつるよし。多くゆるすは神祇・釈教・恋・無常の句、旅にて離るゝ所多し。当流、旅・恋の句難儀にして、又よき句も旅・恋に有( あり) 。」( 『宇陀法師』)
〔句意〕( その家路につく狩人に、) 落武者が野宿の準備をしながら、明日から行こうとしている道程などについて、あれこれと尋ねています。
( 落武者の明日の道問( とふ) 草枕)
森の透間( すきま) に千本の片そぎ翅輪
ナオ・六句目、雑の句。「千本の片そぎ」は、神社の社殿で棟木の端の片方を削いだ形のものをいう。『陸奥鵆』では、「水ことと御手洗の音」で収録されている。ナオ・三句目からの視覚的な景気の句に比して、水音と聴覚的な景気の句である。
「体格は先( まづ) 優美にして、一曲有( ある) は上品( じゃうぼん) 也。又、たくみを取( とり) 、珍しき物によるはその次也。中品( ちゅうぼん) にして多くは地句也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その落武者は、) 行く手の森の隙間から、神社の千本の片そぎを見つけた。そして、その神社は、野宿をするのに適当な所と思われた。
( 森の透間( すきま) に千本の片そぎ)
日中の鐘つく比( ころ) に成( なり) にけり桃里
ナオ・七句目、雑の句。名残の裏からは、桃里も加わり、五吟となっている。「日中」は、正午のこと。
「不易をしらざれば、実( まこと) に知れるにあらず。不易といふは、新古によらず、変化流行にもかゝわ〈大礒義雄校注・は〉らず、誠によく立( たち) たる姿也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その神社の森の辺りで、) 正午を知らせる鐘の音が響いておりました。
( 日中の鐘つく比( ころ) に成( なり) にけり)
一釜( ひとかま) の茶もかすり終( をはり) ぬ曽良
ナオ・八句目、雑の句。「かすり終( をはり) ぬ」は、中に入れたものが少なくなって容器の底をかするようになったということで、場面は外の叙景から一転して茶飲みの叙景となった。
「新( あたらし) みは俳諧の花也。ふるきは花なくて木立ものふりたる心地せらる。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その正午のこと、) 一釜の茶も底を擦るまで飲み尽くしてしまいました。
( 一釜( ひとかま) の茶もかすり終( をはり) ぬ)
乞食ともしらで憂世の物語翅輪
ナオ・九句目、雑の句。「憂世の物語」とは、世間話し程度の意。
「案ずるばかりにて出( いづ) る筋にあるべからず。常( つねに) 務( つとめ) て心の位を得て、感( かんず)るもの動くやいなや句となるべし。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その茶を飲みながらの相手は、) 実は乞食なのだが、それとも知らず、あれこれと、世間話しに興じています。
( 乞食ともしらで憂世の物語)
洞の地蔵にこもる有明翠桃
ナオ・十句目、「有明( 月) 」で秋。名残の表の月の定座を一句引き上げている。
「月は上句( かみのく) 勝( まさり) たるべし。落月、無月の句つゝしむべし。時によるべし。法にはあらずと也。星月夜は秋にて賞の月にはあらず。もしほ句に出( いづ) る時は、す〈大礒義雄校注・素〉秋にし、他季にて有明などする也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その人が乞食と分かったのは、) 洞窟の地蔵尊にお祈りをしていて、有明の月が空に残る明け方になって、その明るさで分かったのです。
( 洞の地蔵にこもる有明)
蔦の葉は猿の泪や染( そめ) つらん翁
ナオ・十一句目、「蔦」で秋。乞食と「其人」の付けが続いたので、芭蕉の遁句( にげく) 〈一巻の進行にねばりが出てきた時など、会釈よりも一層軽い付けをして場面を転回するもので、巧者の人のやることとされている〉の一つと解されている。
「其人: 前句を受けて、前句の動作や行為にふさわしい人物の身分・職業・年齢・性別・身体・癖・性格・着用品・状況・状態・言動などを見定め、これを手がかりにして付けるものである。会釈( あしらい) : 打越からの変化が難しいときなど、前句の人の容姿・持物・衣類または周辺の器材・食物などをもって程よくその場をあしらってゆく方法である。」( 『連句辞典』)
〔句意〕( その洞窟あたりの景色は、) 蔦の葉が紅葉し、それは、きっと、猿の涙で紅く染まったのかも知れません。
( 蔦の葉は猿の泪や染( そめ) つらん)
流人( るにん) 柴刈秋の風桃里
ナオ・折端、「秋風」で秋。折角、芭蕉が遁句と場面転回をしたのに、また、「流人」が現れて、この名残の表は、「述懐」の句が伝染したようである。
「述懐・述懐は文字通り、心中の思いを述べることをいうが、俳諧では通常は世を恨み、老や貧を慨嘆する気持の句をいう。」( 『連句辞典』)
〔句意〕( 蔦の葉は、猿の泪で染まり、) 秋風の吹く中、流人が柴を刈って、冬の薪の支度をしている。
( 流人( るにん) 柴刈秋の風)
今日も又( また) 朝日を拝む石の上蕉
ナウ・折立、雑の句。この名残の裏の折立は、芭蕉の句で始まった。この名残の裏は翠桃を欠いて、芭蕉・二寸・曽良・翅輪・秋鴉・桃里の六吟となっている。すなわち、この歌仙は、表六句が、芭蕉・翠桃・曽良の三吟、初裏の十二句は、翅輪が加わって四吟、名残の裏十二句が、桃里を加えて五吟となり、この名残の裏の六句は、六吟である。この名残の裏の折立の句が、この歌仙での芭蕉の最後の句となる。この歌仙の芭蕉の発句「おふ人を枝折の夏野哉」そして「今日もまた朝日を拝む石の上」と、俳諧師・芭蕉の面目躍如という感が大である。「今日もまた」とは、今日またこの命ありとの実感の表白であろう。「朝日を拝む」には、その命あっての、その風姿の様であろう。「石の上」には、今ここに命あり、そして、漂泊の身の風羅坊・芭蕉その人の境遇の表白であろう。そして、これらのことは、山本健吉著の「芭蕉」( 『芭蕉読本』所収) の次の一節を連想させる。
「発句は芭蕉のはるか以前から、いや、発生の当初から、連句の場を離れて自己充足しようという傾向が見られる。また一方、それはあくまでも連句の場の発句として、付句を欲求する性質を内在させている。少なくとも
芭蕉の発句は、発句の二律背反的性格の微妙なかねあいのうちにあった。一方において、それは十七音詩型のうちに、内容的にも形式的にも、言語表現としての完結を求めようし、他方においては、付句を要求して無限に連鎖しようとする。一方においては、それ自身、一つの認識の刻印として、断定の言葉を投げ出そうとし、他方においては相手に問いかけて、その答えを求めようとする。一方においては、孤独のモノローグに飽くまで徹しようとし、他方においてはダイアローグの声を裏側から響かせようとする。」
すなわち、芭蕉の句は、それが、発句であろうが、付句であろうが、その連句における、そのダイアローグ( 対話) と共に、必ず、芭蕉その人の、詩人の魂としての孤独なモノローグが表白されているのだ。すなわち、言葉を代えていえば、俳諧( 連句) は、芭蕉によって完成されると共に、芭蕉その人によって破られ、今日の俳句という一ジャンルを生み出す要素を、その完成の時から、常に内包していたということなのである。芭蕉の、いずれの句にも、それが、どんなに名のない句であれ、そんな思いが込められているように思えるのである。
「師〈私注・芭蕉〉の曰『此道の我に出( いで) て百変百化す。しかれども、その境、真草行の三つをはなれず。その三つが中にいまだ一二を不尽( つくさず) 』と也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その流人は、) 冷たい石の上に座し、今日あることの生命をいとおしみつつ、大自然への帰依のもとに、今、朝日を拝んでいます。
( 今日も又( また) 朝日を拝む石の上)
米とぎ散( ちら) す瀧の白浪二寸
ナウ・二句目、雑の句。『陸奥鵆』では、「殿付けられて唯のする舟翅輪」とある。どちらにしても、芭蕉の前句の、芭蕉その人の孤独のモノローグには、目が向いていないように思われる。
「松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へと、師〈私注・芭蕉〉の詞のお〈大礒義雄校注・あ〉りしも、私意をはなれよといふ事也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その朝日を拝む行者は、) 滝の水で米をといで、朝餉の支度をしています。
( 米とぎ散( ちら) す瀧の白浪)
籏の手の雲かと見えて飜り曽良
ナウ・三句目、雑の句。『陸奥鵆』では、「奥筋も時は替らずほとゝぎす〕の夏の季語の句で収録されている。
「巧者( こうしゃ) に病あり。師〈私注・芭蕉〉の詞にも『俳諧は三尺の童にさせよ。初心の句こそたのもしけれ』などとたび云( い) ひ出( いで) られしも、皆巧者の病を示されし也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( 米洗う谷川から山上を見上げますと、) 雲が靡いているように、戦いの旗が無数に翻っているではありませんか。
( 籏の手の雲かと見えて飜り)
奥の風雅をものに書( き) つく翅輪
ナウ・四句目、雑の句。『陸奥鵆』では、「噛ずに呑メと投ル丸薬」と全く別形のもので収録されている。『俳諧書留』の方が、奥羽の源頼義父子の前九年・後三年の役などを連想させ、この歌仙に相応しいように思われる。
「高くこゝろをさとりて俗に帰るべしとの教なり。常に風雅の誠をせめさとりて、今なす処俳諧に帰るべしと云( いへ) る也。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その靡く籏を見ていますと、) 奥羽の数々の戦や、それにまつわる連歌などが思い出され、その奥筋へと旅立つ翁の、これからの旅などが偲ばれ、それらのことを書きつけておきたいとと思います。
( 奥の風雅わものに書( き) つく)
珍しき行脚を花に留置( き) て秋鴉
ナウ・五句目、「花」で春。『陸奥鵆』の句形では、「花の宿馳走をせぬが馳走也桃雪」とあり、この桃雪の号は、秋鴉の別号である。「留置き」は、引き留めるの意味。芭蕉等は、事実、『おくのほそ道』紀行で、四月三日から十五日までの長きにわたり、この黒羽に滞在することとなる。その芭蕉等の歓待の中心人物が、この秋鴉こと、浄法寺図書高勝ということになろう。その秋鴉が、この歌仙の最後の、花の定座を担当し、この歌仙全体の構成に花を添えているという趣である。
「飛花落葉の散乱( みだる) るも、その中にして見とめ聞とめざれば、お〈大礒義雄校注・を〉さまることなし。その活( いき) たる物だに消( きえ) て跡なし。又、句作りに師の詞有( あり) 。物の見へ〈大礒義雄校注・え〉たるひかり、いまだ、心にきえざる中にいひとむべし。」( 『三冊子』)
〔句意〕( その奥筋へと旅立つ翁を、) この満開の花に事寄せて、旅の主客として、引き留めています。
( 珍しき行脚を花に留置( き) て)
弥生暮( くれ) ける春の晦日( つごもり) 桃里
挙句、「春の晦日」で春の句。「弥生」は、陰暦の三月で春の末である。「挙句は付( つか) ざるをよしと古説有( あり) 。今一句に成( なり) て、一座興覚( さむ) る故也。また、兼て案じ置くとも云( いへ) り。」( 『三冊子』) すなわち、挙句は、あらかじめ作って用意しておくものともいわれている。余瀬の本陣問屋の主人・蓮見桃里が、執筆( 書記役) のような形で、この最後の歌仙を締め括っている。
「弥生暮( くれ) ける」には、この歌仙にピリオドがうたれることの惜別の情が込められていようし、「春の晦日( つごもり) 」には、花も過ぎれば留め置くこともかなわないという惜春そして惜別の情も込められていよう。「弥生暮( くれ) ける」と「春の晦日( つごもり) 」の二重のリフレインも印象的である。なお、『陸奥鵆』では、「ふさぐというて火燵そのまゝ」の句形で収録されている。
「学ぶことつねに有( あり) 。席に望〈大礒義雄校注・臨: のぞみ〉て文台と我と、間( かん) に髪( はつ) をいれず、思ふ事速( すみやか) に云出( いひいで) て、爰( ここ) に至( いたつ) て迷ふ念なし。文台引おろせば即反故( ほんご・ほうぐ) 也。」( 『三冊子』)
〔句意〕弥生のつごもりとなって、花が、今、終わろうとしていますが、私たちの、この風雅な饗宴も、その桜花と同じように、静かに幕を閉じようとしています。( 時あらばまた、この黒羽の里で、花の季節に貴方達と、再び、このような饗宴をしたいと切に思うものです。)
【補注・付記】
① 東明雅氏は、「俳諧に現代語訳をつけるのは蛇足かも知れないが、句意をどのくらい正確に理解しているか、それは結局は現代語訳にあらわれるものである。現代語訳を付けることは容易のようで難しく、誤魔化しがきかない。だから、作品鑑賞をする場合、自分の立場を明確にするためにも、現代語訳は必要で、現代語訳を付けないで曖昧なことを述べる批評や鑑賞を、私は信用できない」( 『連句入門』) と指摘している。
このように、歌仙一巻( 三十六句) の全部に現代語訳を付ける困難さの故に、俳諧( 連句) 鑑賞から、研究者はともかくとして、実作者( 特に、俳句作家) また一般の鑑賞者を遠ざける最大の理由となっているとも思われる。すなわち、歌仙一巻・三十六句の全部を正確に理解するということは、これは甚だ困難なことであり、このことが、俳諧( 連句) という分野の裾野を閉ざしているということと、そして、そのことが、連俳非文学論( 正岡子規) などを生む素地の一つの理由とも思えるのである。このことに関し、あの博覧強記の、柳田国男氏ですら、かく嘆いているのである。
「前代の俳諧のごときは殊に読者を限定して、いわば銘々の腹の中のわかる者だけで鑑賞し合い、今日存する篇汁( へんじゅう) はその楽しみの粕のようなものである。時代が改まって程なく不可解になるのも自然であった。面白味の判らぬだけならまだ曲従することもできる。わかったような顔もしていられるが、どう考えても全然意味がとれない句、または人によって解説の裏はらになったものさえある。」( 『木綿以前の事』所
収「生活の俳諧」)
とすれば、俳諧( 連句) 愛好者は、他人の批判を恐れることなく、今の、そして、自分の、限られた知識と経験とを最大限に披露して、誤った理解と罵られようが、俳諧( 連句) 関連の情報を沢山提供しあうこと、このことが、今、何よりも重要なことであって、そして、そのような積み重ねが、必ずや、世界に類を見ない独自文学形態の「俳諧之連歌」( 連句) の再生を促すものと、そんな思いを強くするのである。
「歌仙は三十六歩也。一歩も後に帰る心なし」( 『三冊子』) 、すなわち、躊躇することなく、自分の付句( 考え方・理解) を場に晒すこと、これが、俳諧( 連句) 愛好者の第一歩と、そんな思いを強くするのである。そして、まだまだ未知で未開拓の世界である芭蕉以外の俳諧( 連句) を鑑賞するための、数多くの文献や情報が容易に一般の人にも手に入ることのできるようになることを切に願うものである。
② 俳諧( 連句) を鑑賞する上で、意味不明( 現代語訳不明) の場合、東明雅氏( 『連句入門』) の、付合( 付けの種類) 、付心( 付けの手法・態度) 、付所( 付けの狙いどころ・手がかり) 、付味( 付けの効果) の観点からの鑑賞は、大変に有効な道具立てと思われた。参考に、以下、要約しておくこととする。
Ⅰ 付合( 付けの種類)
ⅰ 物付( 前句の詞や物の縁によって付けるのをいう。)
ⅱ 心付( 物付のように前句の詞や物に頼らずに、前句のあらわす全体の意味や心持に応じて付けていく方法
「句意付」を指す。)
ⅲ 余情付( 広義の心付で、「移り・響・匂ひ・位」などの余情を主として付けていく方法を指す。)
Ⅱ 付心( 付けの手法・態度)
Ⅲ 付所( 付けの狙いどころ・手がかり)
Ⅳ 付味( 付けの効果)
※ 付心と付所については、次表の各務支考の七名八体説によっている。
【参考文献】【主要参考文献】記載のものの他に、次の図書を参考とした。
1 『芭蕉連句集』・中村俊定・他校注・岩波文庫・昭和五〇
2 『俳人名言集』・復本一郎著・朝日文庫・平成四
3 『芭蕉連句抄( 第七篇) 』・阿部正美著・明治書院・昭和五六
4 『蕉門俳論俳文集( 古典俳文体系1 0) 』・大礒義雄・他校注・集英社・昭和五一
登録:
投稿 (Atom)